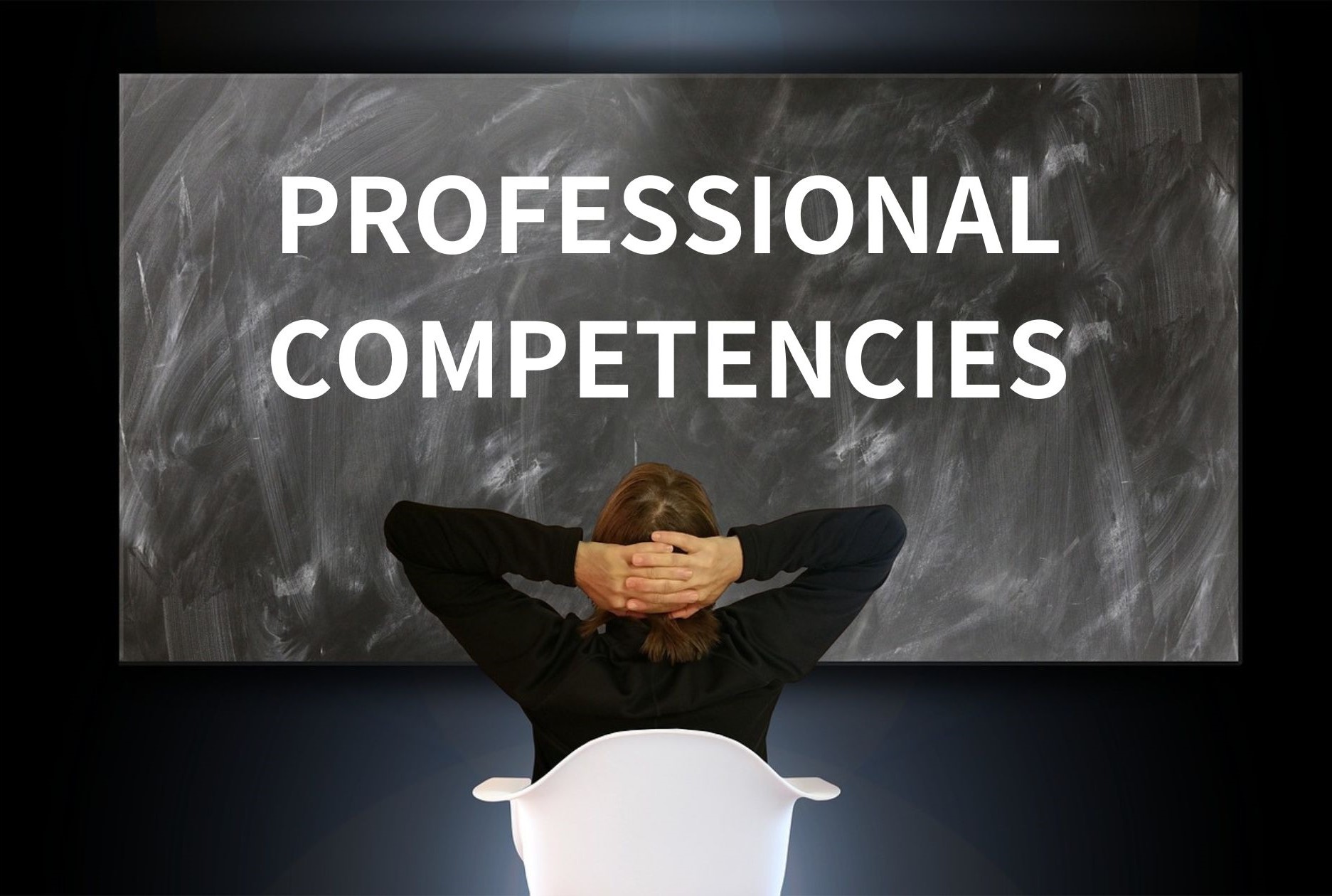技術士第二次試験の合格基準となるコンピテンシーが令和5年1月に部分改訂されました。今回の改訂箇所を確認しながら筆記試験・口頭試験への影響を考察していきます。
技術士の制度変更を強調した前文
技術士コンピテンシーの前文には、今回改訂した背景やポリシーが、3つのセクションで書かれています。前文はやや長文なので、セクションごとに分けて考察していきます。
前文セクション1:第1段落~第2段落
技術の高度化、統合化や経済社会のグローバル化等に伴い、技術者に求められる資質能力はますます高度化、多様化し、国際的な同等性を備えることも重要になっている。
技術者が業務を履行するために、技術ごとの専門的な業務の性格・内容、業務上の立場は様々であるものの、(遅くとも)35歳程度の技術者が、技術士資格の取得を通じて、実務経験に基づく専門的学識及び高等の専門的応用能力を有し、かつ、豊かな創造性を持って複合的な問題を明確にして解決できる技術者(技術士)として活躍することが期待される。
セクション1は、技術士に求められる資質能力の背景と概念が書かれています。
第1段落には、①技術が高度化・統合化しているので資質能力も高度化・多様化している、②社会経済がグローバル化しているので資質能力の国際的同等性が重要になる、という2つの背景が書かれています。①は改定前と変わっていません。②は今回の改訂で付け加えられた箇所で、国際的同等性の重要性が強調されています。
第2段落は、改訂前とまったく同じで、技術士として活躍するためには、いつまでにどのような資質能力を修習すべきかが書かれています。35歳までに修習すべき資質能力は、専門的学識や高等の専門的応用能力だけではなく、複合的な問題を明確にして解決できる能力だとしています。このことから、技術士法で規定する専門的学識や高等の応用能力だけでは、複合的な問題は解決できないということがわかります。
前文セクション2:第3段落~第4段落
技術士に求められる資質能力(コンピテンシー)については、国際エンジニアリング連合(IEA)が定める「修了生としての知識・能力(GA; Graduate Attributes)と専門職としてのコンピテンシー(PC; Professional Competencies)」に準拠することが求められている。2021年6月にIEAにより「GA&PCの改訂(第4版)」が行われ、国際連合による持続可能な開発目標(SDGs)や多様性、包摂性等、より複雑性を増す世界の動向への対応や、データ・情報技術、新興技術の活用やイノベーションへの対応等が新たに盛り込まれた。
技術士制度においては、IEAのGA&PCも踏まえ技術士試験やCPD(継続研さん)制度の見直し等を通じ、我が国の技術士が国際的にも通用し活躍できる資格となるよう不断の制度改革を進めている。
セクション2の全文は、今回の改訂で追加されたものです。第1段落では、①技術士コンピテンシーがIEA-GA&PCに準拠していること、②IEA-GA&PCは21年6月に第4版に改訂されていることの2点が書かれています。
①は以前からアナウンスされていたことです。注目すべきは②で、今回の技術士コンピテンシーは、IEA-GA&PC第4版の内容に整合するよう改訂されたという点です。前回のGA&PC第3版の改訂が2013年だったので、2021年の第4版改訂は8年ぶりとなります。その間、2015年にSDGsが採択され、第4版は主にSDGsを反映した改訂内容になっていることが重要なポイントです。
第2段落では、IEA-GA&PCを踏まえて技術士制度の改革を継続的に進めていることが書かれています。GA&PCに基づくコンピテンシーは、技術士制度の重要な位置づけになっていることがわかります。しかし、制度を定める技術士法や施行令・施行規則では、コンピテンシーの位置づけは規定されていません。今後の方向性も示していないことから、当面はコンピテンシーの法的位置づけを曖昧にしたまま制度改革を進めるということのようです。
前文セクション3:第5段落
セクション3も、今回の改訂で追加された内容です。ここでは、SDGsの達成やSociety5.0の実現に向けた科学技術・イノベーションの推進が技術士の役割であり、今後もGA&PCに基づくコンピテンシーを技術士制度に反映させていくことを明言しています。つまり、技術士制度の目的が、技術士法で定める科学技術の向上・国民経済の発展から、SDGsの達成・Society5.0の実現に変わっていると理解できます。
第二次試験は、技術士法で定める専門的学識及び高等の専門的応用能力を確認する試験だと案内されます。ところが、実施される試験の内容は、複合的な問題を解決に必要なコンピテンシーの確認です。技術士法を改正しないまま制度変更しているので、試験案内と実施内容が異なる状況となっているのです。今回のコンピテンシー改訂により、そのギャップがさらに広がったように感じます。
改訂された4つのコンピテンシー
技術士コンピテンシーは8つありますが、今回改訂されたのは、問題解決、コミュニケーション、技術者倫理、継続研さんの4つです。それぞれの改訂箇所を赤文字で示しながら、改訂内容を見ていきます。
「問題解決」の改訂内容
- 業務遂行上直面する複合的な問題に対して、これらの内容を明確にし、必要に応じてデータ・情報技術を活用して定義し、調査し、これらの背景に潜在する問題発生要因や制約要因を抽出し分析すること。
- 複合的な問題に関して、多角的な視点を考慮し、ステークホルダーの意見を取り入れながら、相反する要求事項(必要性、機能性、技術的実現性、安全性、経済性等)、それらによって及ぼされる影響の重要度を考慮した上で、複数の選択肢を提起し、これらを踏まえた解決策を合理的に提案し、又は改善すること。
1番目の項目では、複合的な問題に対して、必要に応じてデータ・情報技術を活用して定義することが追加されました。社会経済の複雑化や自然環境の劇的変化が進む状況において、解決すべき複合的な問題は、ますます見え難くなっています。そのため、デジタルデータやITを活用して「複合的な問題を見える化」する必要性を、今回の改訂で加えたものと理解できます。
2番目の項目では、解決策の提案に当たって、多角的な視点を考慮すること、ステークホルダーの意見を取り入れることの2点が追加されています。これは、前文のセクション2にも書かれていたように、多様性と包摂性の理念を取り入れたものです。複合的な問題は、様々なリスク要因が含まれる問題です。そのため、多角的な視点からリスクを評価する必要があり、利害関係者の多様な意見を取り入れることが加えられたと理解できます。
「コミュニケーション」の改訂内容
- 業務履行上、情報技術を活用し、口頭や文書等の方法を通じて、雇用者、上司や同僚、クライアントやユーザー等多様な関係者との間で、明確かつ包摂的な意思疎通を図り、協働すること。
- 海外における業務に携わる際は、一定の語学力による業務上必要な意思疎通に加え、現地の社会的文化的多様性を理解し関係者との間で可能な限り協調すること。
コミュニケーションでは、1番目の項目に、情報技術の活用する、包摂的な意思疎通を図る、協働する、の3点が追加されています。
コミュニケーションにおける情報技術の活用については、メール、チャット、SNS、リモート会議などが、すでに活用されているので、いまさら説明は不要と思います。ただし、情報技術の活用目的が、明確かつ包摂的な意思疎通であることをしっかり認識しておく必要があります。
包摂的な意思疎通とは、ステークホルダーやユーザーとのコミュニケーションを通じて、相互にリスク認識を正しく共有するということだと考えます。技術士の業務活動では、高度な科学技術を取り扱うので、専門技術によるリスクを専門知識の無い公衆に正しく伝える必要があります。リスク共有では、一方向では正しく伝わらない可能性があるため、双方向での意思疎通も必要になります。
最後に追加された「協働する」とは、業務遂行に当たって必要なコラボレーション能力を規定したものです。複合的な問題は一人の技術者のみで解決できないので、複数の技術者がコラボレーションする必要があります。技術士の業務では、協力し合う能力、目標を共有する能力、役割を理解する能力、リスク情報を受発信する能力などが必要だと考えます。
「技術者倫理」の改訂内容
- 業務遂行にあたり、公衆の安全、健康及び福利を最優先に考慮した上で、社会、経済及び環境に対する影響を予見し、地球環境の保全等、次世代にわたる社会の持続可能な成果の達成を目指し、技術士としての使命、社会的地位及び職責を自覚し、倫理的に行動すること。
- 業務履行上、関係法令等の制度が求めている事項を遵守し、文化的価値を尊重すること。
- 業務履行上行う決定に際して、自らの業務及び責任の範囲を明確にし、これらの責任を負うこと。
1番目の項目では、「経済」が赤文字になっていますが、ここは初版では「文化」と書かれていた箇所です。また、1番目の項目では、「持続可能な成果の達成を目指す」ことも追加されています。これらは、GA&PC第4版の表記に合わせたものです。GA&PCでは、経済的、社会的、環境的影響を認識して持続可能なアウトカムが得られるよう業務活動することを要求しています。
これと同様の内容は、R5.03改訂の「技術士倫理綱領」でも明示されています。倫理綱領の改訂では、これまでの「持続可能性の確保」という表記を「持続可能な社会の実現」に変更し、技術士の行動目標を明確化しています。「社会の持続可能な成果の達成」は、技術者の倫理要件における重要なポイントになると考えます。
2番目の項目に加えられた「文化価値を尊重」は、SDGsに基づく多様性・包摂性の尊重が反映されものです。GA&PC第4版でも、文化的要件を満足することが加えられています。
国内でも、地域により経済環境、生活習慣、風土は異なります。首都圏の価値観で決めた施策が、地方の価値観の下で有効に機能するとは限りません。技術士の業務活動では、法制度を遵守することだけではなく、特有の文化的要件を踏まえて業務成果の影響による差別化を無くすことも求められます。
「継続研さん」の改訂内容
- CPD活動を行い、コンピテンシーを維持・向上させ、新しい技術とともに絶えず変化し続ける仕事の性質に適応する能力を高めること。
継続研さんの規定文は全面的に変更されていますが、内容的にはこれまでと大きく変わっていません。
注目したいのは、「絶えず変化し続ける仕事の性質に適応する」という表記です。技術士の仕事は、複合的な問題を技術的に解決することです。複合的な問題は、複数のリスクが複雑に絡む問題で、リスクの大きさは時間や環境により変化する特性があります。
また、技術士が扱う専門技術や問題分析技術も、日々進化しています。変化と進化に適応できなければ、複合的な問題を解決する仕事は継続できません。そのため、技術士の資格を取得後も、CPD活動を行い複合的な問題の解決に必要なコンピテンシーを高めていく必要があるわけです。
コンピテンシー改訂による試験への影響
コンピテンシーは、第二次試験合格に必要な基準なので、今回の改訂内容は試験内容や採点基準に必ず影響するはずです。影響がどの程度になるか断定はできませんが、現時点で考えられることを挙げておきます。
筆記試験への影響
必須科目Ⅰ・選択科目Ⅲの設問(1)
「問題解決」において、複合的な問題を定義することが明記されたことから、必須科目Ⅰ・選択科目Ⅲの設問(1)では、複合的な問題の特定を含めて課題抽出が問われるかもしれません。あるいは、課題抽出の採点では、公表データ・数値根拠の提示を加点減点の判断材料にすることも考えられます。
必須科目Ⅰの設問(4)
「技術者倫理」において、持続可能な成果の達成を目指すことが追加されたことから、必須科目Ⅰの設問(4)では、これまでの「社会の持続性の観点」が「持続可能な社会の達成に向け」などの表記に変更されると考えられます。採点では、社会・経済・環境に対する影響を踏まえて持続可能な社会の達成に向けた要点・留意点がポイントになりそうです。これまでのように、自然環境の保全だけでは、不十分と判定されそうです。
選択科目Ⅱ-2の設問(3)
選択科目Ⅱ-2の設問(3)は、マネジメントを確認する設問ですが、「コミュニケーション」において、包摂的な意思疎通が追加されたことにより、関係者とのリスク共有方策が問われるかもしれません。また、「コミュニケーション」では、情報技術の活用や協働も追加されています。そのため、これまで通り関係者との調整方策を問われるとしても、高得点を得るにはICTを活用した調整方策の効率化、効果的な連携方策などの解答が必要になると考えます。
口頭試験への影響
口頭試験は、コミュニケーション・リーダーシップ、評価・マネジメント、技術者倫理、継続研さんの6つのコンピテンシーを対象に採点しています。このうち、コミュニケーション、技術者倫理、継続研さんの3つのコンピテンシーが今回改訂されていています。それ以外にも、問題解決の改訂内容が、リーダーシップ、評価、マネジメントに関連しており、全ての試問事項に影響すると考えます。
今回改訂されたコンピテンシーを確認するために、口頭試験では次のような質問が加わるかもしれません。
- 包括的な意思疎通で普段工夫している点とは?
- 関係者の意見をどのように取り入れているか?
- 詳述業務の成果はSDGs達成に寄与できるか?
- データ活用のマネジメントは普段どうしてる?
- 持続可能な社会の達成のために重要なことは?
- 新技術への適応に向けて取組んでいることは?
改訂版コンピテンシーは、令和8年度の第二次試験から適用されます。受験予定者は、口頭試験で使われる業務経歴・業務内容の詳細を4月に提出しなければなりませんから、改訂版コンピテンシーを踏まえた早めの準備が必要になりそうです。