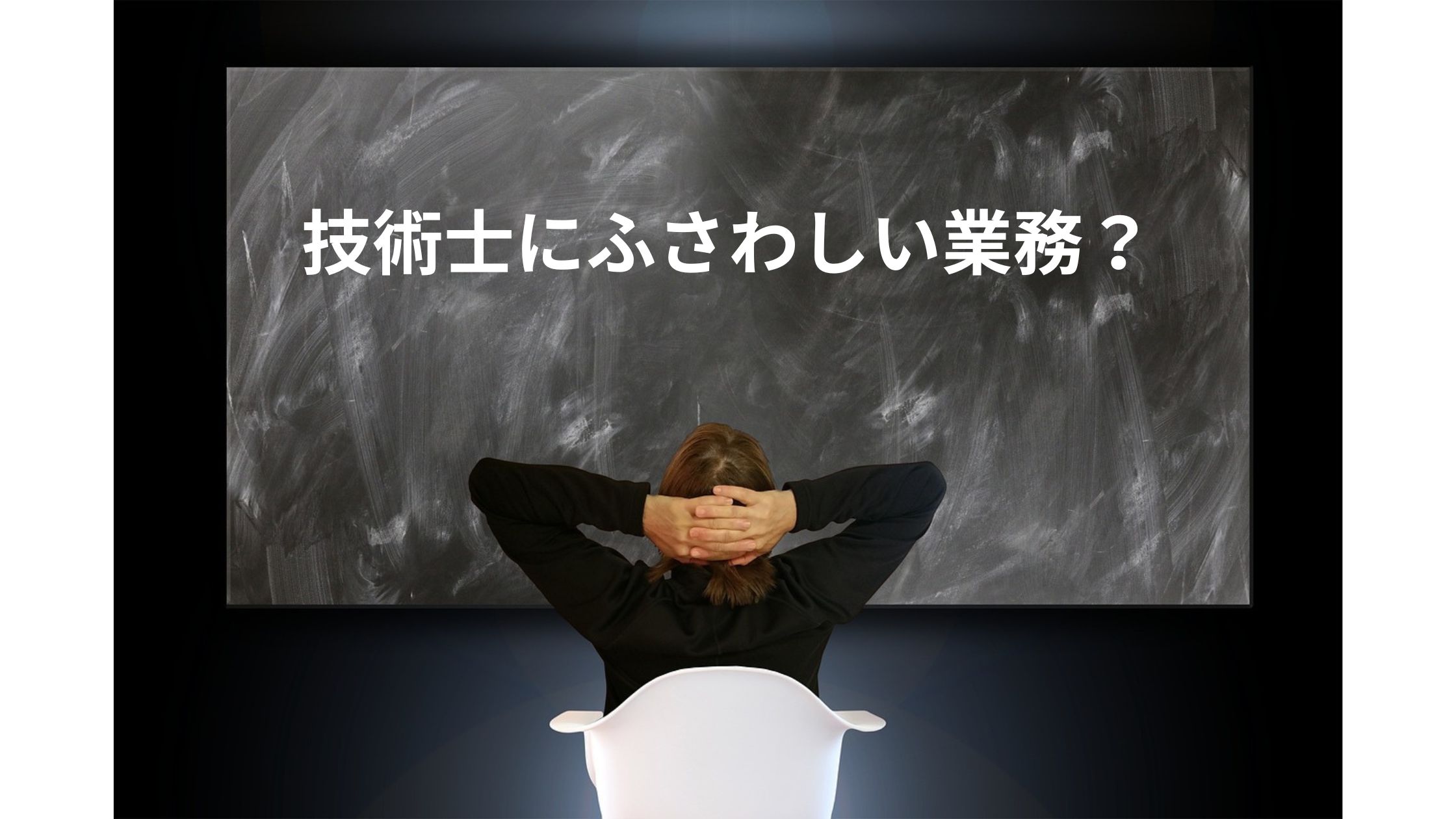現在のコンピテンシー確認型試験では、技術士法を無視した方が、技術士にふさわしい業務経歴を簡単に書くことができます。今回はその理由について解説していきます。
技術士法から見る「技術士にふさわしい業務」の意味
国家資格試験は、法的根拠に基づいて実施されます。技術士試験も、技術士法に基づき筆記試験と口頭試験を実施しています。技術士法は、昭和32年に制定された古い法律です。第2条の技術士の定義に書かれている「高等の専門的応用能力」という言葉は、制定当初から約70年にわたり使われ続けています。
第二次試験の受験申込み案内では、技術士法第6条で定めている受験資格要件に従って、「専門的応用能力を必要とする業務経歴」を提出するよう指示されています。受験申込み段階では、業務の要件に「高等」という言葉は使われていません。経歴票に書かれている業務が高等か否かは、口答試験において確認されます。
そのため、技術士法から見る技術士にふさわしい業務は、技術士法が定義する「高等の専門的応用能力を必要とする業務」だと古くから考えられています。
IEA-PCから見る「技術士にふさわしい業務」の意味
第二次試験の採点対象となっている技術士コンピテンシーは、IEA-PC(国際エンジニアリング連合のプロフェショナル・コンピテンシー2013)を満たすように平成28年に制定されました。
技術士コンピテンシーでは、8項目すべてに「業務」という言葉が使われています。EA-PCでは、この「業務」に当たる言葉を「複合的な活動」と表現しており、次の5つの特性が複数又は全部含まれると明確に定義しています。なお、IEA-PCは難解な文章で書かれているので、私なりの解釈に基づき平易な表現で要約しています。
複合的な活動に含まれる5つの特性
特性1:多様なリソースの活用を含む
特性2:相互作用の最適解決が必要
特性3:革新的解決策の導出が必要
特性4:社会環境に重大影響が及ぶ
特性5:原理に基づくアプローチを適用
このうち、特性1はリソースマネジメント、特性5は原理に関する専門知識が要求される業務特性であり、すべての業務が対象です。これに対して、特性2,3,4は、個別業務に含まれる問題特性です。
特性2,3,4を含む問題は、現時点で明白な解決策が無い、いわゆる「複合的な問題」です。このような複合的な問題を解決するには、適切な問題解決プロセスを遂行し、社会環境へのインパクトを評価し、結果に責任を負う資質能力が要求されます。これに特性11,5で要求しているリマネジメントと専門知識を加えると、技術士コンピテンシーとほぼ同じです。
そのため、IEA-PCから見る技術士にふさわしい業務は、「複合的な問題を解決する業務」だと理解できます。現在の口頭試験では、複合的な問題を解決した実務経験を確認するためにコンピテンシーをどのように発揮したかを確認しています。
試験制度により「技術士にふさわしい業務」の意味が変化
受検申込み時に提出する業務経歴は、口頭試験において使われます。平成30年度までの旧試験制度では、業務経歴を参考にして「業務経歴と応用能力」を口頭試験で確認していました。応用能力の判定基準が明確に示されていなかったため、技術士にふさわしい業務の具体的内容は、口頭試験合格者の経験談などから判断されていました。
一方、令和元年度以降の現行試験制度では、業務経歴を参考にして「技術士としての実務能力」を確認することになっています。技術士としての実務能力は、コミュニケーション、リーダシップ、評価、マネジメントの4つのコンピテンシーを対象に判定されます。IEA-PCの考えに基づくと、これらのコンピテンシーを発揮した業務は、「複合的な問題を解決した業務」だということです。
このように、平成と令和では技術士にふさわしい業務の意味や判断基準が変化しています。現行のコンピテンシーを確認する試験制度においては、「技術士にふさわしい業務は、複合的な問題を解決した業務」だと捉える方が妥当です。
技術士法が定義する業務に限定する必要はない
技術士法第2条では、「技術士とは、高等の専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関する指導の業務を行う者」と定義しています。そのため、業務経歴では「計画、研究、設計、分析、試験、評価」の業務しか書けないと思われがちです。
しかし、複合的な問題を解決した業務を、これらの限られた業務のみで表現するのは難しく、詳述するストーリーと経歴欄の業務内容が合わなくなる危険性もあります。例えば、詳述するストーリーが、「老朽化部材の強度試験を計画し、強度分析を行い、対策案の有効性を評価して補修設計に反映した」とする場合、「試験、計画、分析、評価、設計」の単語から一つ選んで業務内容を表わすことは困難です。
これまでの添削経験から言えることは、技術士法で定義する業務を書かずに業務経歴を提出して合格しているケースが非常に多いということです。実際には、技術士法の定義に無い「調査、検討、立案、策定、施工、管理、診断」などの業務表記が多く、私も受験の際には、経歴票に「検討」の業務表記を多用していました。最近では、DX/GXイノベーションに関連して、「開発」という業務表記も見られます。口頭試験で指摘を受けた話は、これまで聞いたことが無いので、試験官も問題視していないと思います。
技術士法が定義する業務表記に限定しない方が、業務経歴の書き方のバリエーションが広がり、複合的な問題の解決も伝わりやすくなります。
技術士にふさわしい業務の選定指標を設定する
経歴票に技術士にふさわしい業務を書くためには、どのような複合的な問題を解決したのかを示す必要があります。
先に説明したように、IEA-PCの複合的な活動によれば、個別の複合的な問題に含まれる特性は3種類あります。これらの特性を踏まえると複合的な問題の解決パターンは、①トレードオフ問題の解決、②マニュアル不在問題の解決、③事故欠陥リスク問題の解決の3パターンに分類できます。
これらの3パターンから経歴票に書く経験業務を選定すれば、コンピテンシーを発揮して複合的な問題を解決した「技術士にふさわしい業務」を経歴票に書くことができます。個々の経験業務はそれぞれ違うので、次のように自分なりにわかりやすい指標を設定しておくと、技術士にふさわしい業務を見つけやすくなると思います。
技術士にふさわしい経験業務の選定指標(例)
指標1:品質確保に必要なコストや時間が足りなくて困った業務
指標2:現場条件から標準マニュアルが適用できずに困った業務
指標3:人身事故や環境汚染を防ぐために少し工夫を加えた業務
まとめ
技術士法の定義は、IEA-PCよりあるか昔に定められています。IEAは国際機関であり、日本の技術士法を踏まえてPCを定めたわけではありません。そのため、技術士法における「高等の専門的応用能力」と、IEA-PCをベースとする「技術士のコンピテンシー」は、そもそも無関係だと考えるのが妥当です。
技術士は国家資格なので、資格を定めている技術士法に準拠して受験手続を案内しなければなりません。一方で、現在の技術士口頭試験では、経験業務の中でコンピテンシーをどのように発揮しているかを確認しなければなりません。ですから、受験手続と試験内容は、大きく異なっているのが実態だと言えます。
実務経験証明書の業務経歴に「技術士にふさわしい業務」を書くことは、今も昔も変わりありませんが、その業務内容が令和元年度から大きく変わっています。したがって、現在の試験制度では、技術士法を無視した方が、口頭試験に合格しやすい業務経歴を簡単に書くことができるというわけです。