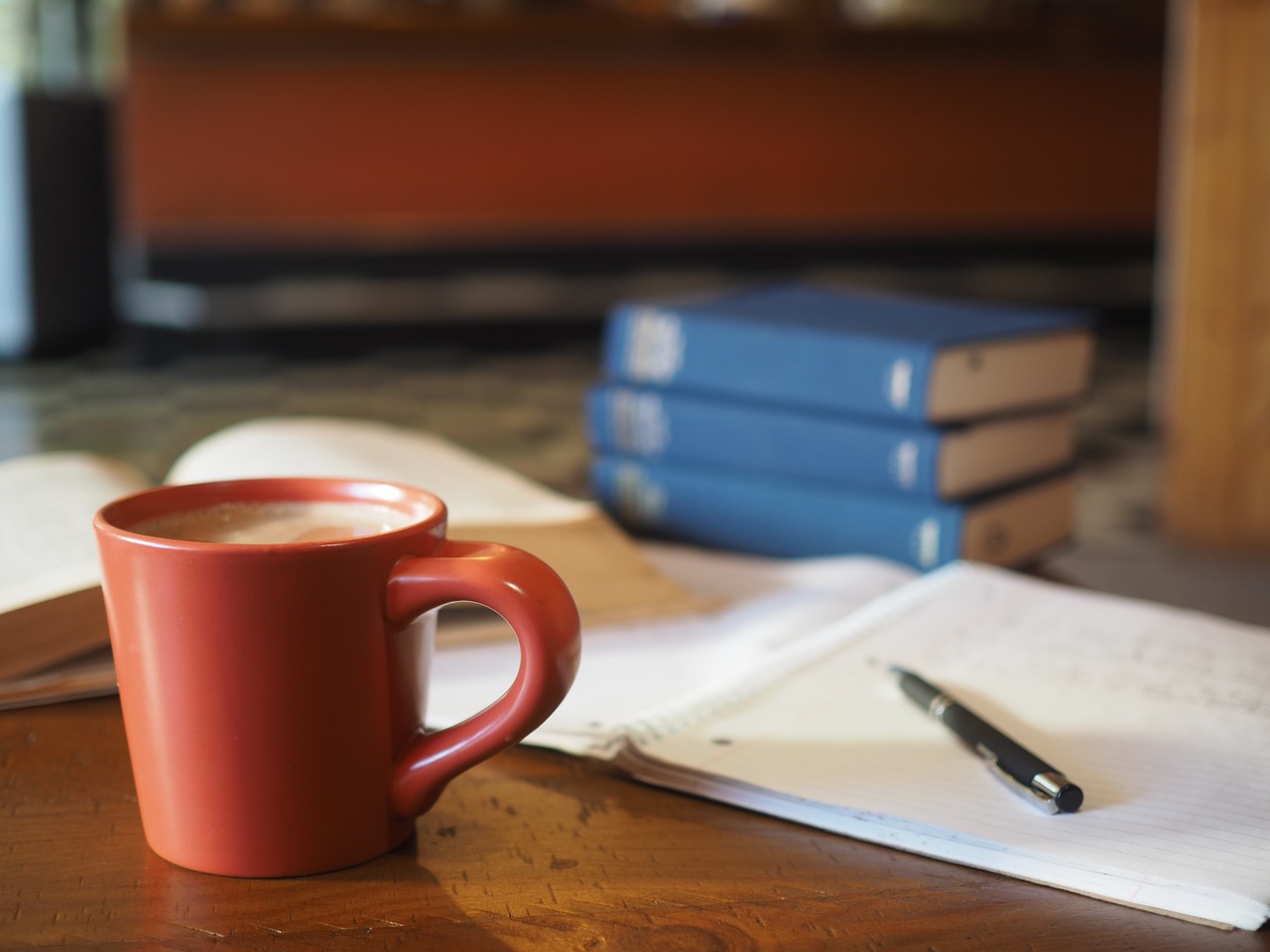口頭試験の「技術士としての実務能力」に関する試問について、ちょっと回答し難い質問を5つ選び、質問趣旨と回答の仕方を解説します。コンピテンシーの本質を突く質問に対応でるように準備しておきましょう。
技術士レベルの資質能力を要した点は?
「詳述した業務で技術士レベルの資質能力が必要だった点は?」と質問を受けた場合、上手く答えることができるでしょうか。
技術士レベルの資質能力とは、「技術士に求められる資質能力(コンピテンシー)」だということは、多くの受験者が知っているはずです。しかし、技術士レベルの資質能力を要する業務を説明できる受験者は少ないように思います。
技術士のコンピテンシーは、IEA(国際エンジニアリング連合)が定めるPC(Professional Competencies)に準拠して定義しています。IEAでは、PCを必要とする複合的な活動(Complex Activities)も別途定めています。技術士のコンピテンシーに使われている「業務」という言葉は、IEAが定める複合的な活動のことです。IEAでは、複合的な活動には次の5つの特性が複数含まれると規定しています。
<複合的な活動に含まれる5つの特性>
特性1:人材・材料・情報など多様な資源が必要
特性2:要求性能・検討事項がトレードオフ関係
特性3:マニュアルが無い又は適用できない
特性4:判断ミスが重大な欠陥・事故につながる
特性5:類似事例や研究事例が無い
上記の特性を用いて詳述業務の問題点を示すと、技術士レベルの資質能力(コンピテンシー)を要した点が回答しやすくなります。
- 重大な事故を回避するために、標準要領の適用を工夫して合理的に解決した点
- マニュアルや類似事例が無かったので、妥当性を評価しながら問題解決した点
- 品質と納期がトレードオフとなり、限られた資源の配分を工夫して解決した点
効果的な意志疎通とはどういう意味か?
「コミュニケーションで留意していることは?」との質問に対して、「明確かつ効果的な意志疎通に留意しています」と回答する人は多いと思います。そこで試験官が納得してくれればよいのですが、「効果的な意思疎通とはどういう意味ですか?」と追っかけ質問が来たら即答できるでしょうか。
技術士に求められるコミュニケーションとは、単なる説明能力ではなく、意思疎通能力です。意志疎通とは相互理解のことで、技術士業務では技術的リスクの相互理解が極めて重要です。
技術的リスクとは、高度な専門知識と豊富な経験を有する技術者が知り得るリスクです。業務を遂行する技術者は、クライアントやユーザーなど、技術的リスクを知らない関係者にリスクを説明し理解してもらう責任があります。また、技術者には、説明を受けた関係者が懸念するリスクを把握し、それに対応する責任もあります。
効果的な意思疎通について、「業務上の技術的リスクをクライアントやユーザーなどの関係者と相互理解できるようにすることです」と説明すれば、試験官はそれ以上追及しないと思います。
リーダー以外もリーダーシップは必要?
「リーダー以外の担当者にもリーダーシップは必要ですか?」との質問に対して、「関係者との利害調整のために必要です」と回答しても、試験官は納得しないかもしれません。
通常の業務は、一人のリーダーと複数の担当者で行いますが、担当者全員がクライアントと利害調整できるわけではありません。
リーダー以外の担当者にとってのリーダーシップを説明するには、各担当者の利害関係者を明確にする必要があります。例えば末端の担当者の場合、業務管理者や直属の上司、同じ業務を担当する同僚、業務で使うデータの提供者、業務結果の使用者は、全て利害関係者になります。利害関係者がいる以上、末端の担当者もリーダーシップは必要になります。
業務の一部しか担当していなくても、業務全体の成果を上げるために、自分が担当した部分について、上司と協議をした経験があれば、それはリーダーシップを発揮した経験と言えます。また、発注者と直接話をする立場になかったとしても、発注者との協議資料作成に携わっていたのであれば、協議者を通じて発注者と利害調整を行ったことになります。
担当者もリーダーシップが必要な理由を問われた場合は、「各担当者の成果が、業務全体の品質に大きく影響するので、担当者にも利害調整能力は必要」と説明すれば、試験官も納得してくれると思います。
詳述業務におけるマイナス波及効果は?
口頭試験では、「詳述業務をどのように評価していますか?」と質問されることがあります。この質問は、業務の波及効果の評価を聞かれているので、プラス波及効果よりもマイナス波及効果(負の影響)を回答した方が試験官は納得すると思います。納得した回答が得られないと、「詳述業務におけるマイナス波及効果は?」とズバリ聞かれるかもしれません。
コンピテンシー「評価」の定義で使われている波及効果とは、IEA-PCの「impacts(インパクト)」を翻訳したものです。波及効果と聞くと良い影響をイメージしがちですが、IEAでは悪い影響という意味で使っているようです。
IEAの倫理行動規範には、回避可能な影響(avoidable impacts)を最小にするという規定があります。日本の技術士倫理綱領は、このIEAの倫理行動規範に適合するよう規定しており、23年3月の改訂版では2.(2)において「影響」という表記を「負の影響」に修正しています。
口頭試験の試験官は、詳述業務の評価を質問することによって、業務成果に対する負の影響の評価能力と改善能力を確認していると思われます。筆記試験でプラス波及効果のみ回答した人は、詳述業務のマイナス波及効果を確認される可能性があるので、準備しておいた方が良いでしょう。
あなたにリソース配分の権限はあった?
マネジメントの質問に対して、リソースの最適配分を回答する人は多いと思います。でも、人材や金銭などのリソースを配分するには、それなりの権限が必要です。通常の場合、リソースの配分を決定できるのは、組織長やリソース管理者であり、各担当者が人員やコストを勝手に動かすことはできません。
コンピテンシーの定義では、業務全体のリソース配分を要求しているように読めますが、IEA-PCでは複合的な業務活動の一部または全体のマネジメントを要求しています。つまり、業務の一部しか担当していなくても、担当業務を成功させるためにマネジメント能力は必要になります。
担当者にも、担当業務に関する品質・コスト・納期の要求事項はあったと思います。その要求事項を満足するために、データ・ソフト・通信ツールなど様々なリソースを駆使したのであれば、それはリソースの最適配分を経験したと言えるでしょう。また、要求事項を自分一人で満足できるか、あるいは応援が必要かの判断をしたのなら人的管理も行ったことになります。
詳述業務におけるマネジメントを説明する場合、あなたの担当範囲(役割)を明確にして、与えられた要求事項と要求事項を満足するために使ったリソースを整理しておくことが重要です。そうすれば、担当業務におけるリソースの最適配分を経験したことが回答できるはずです。