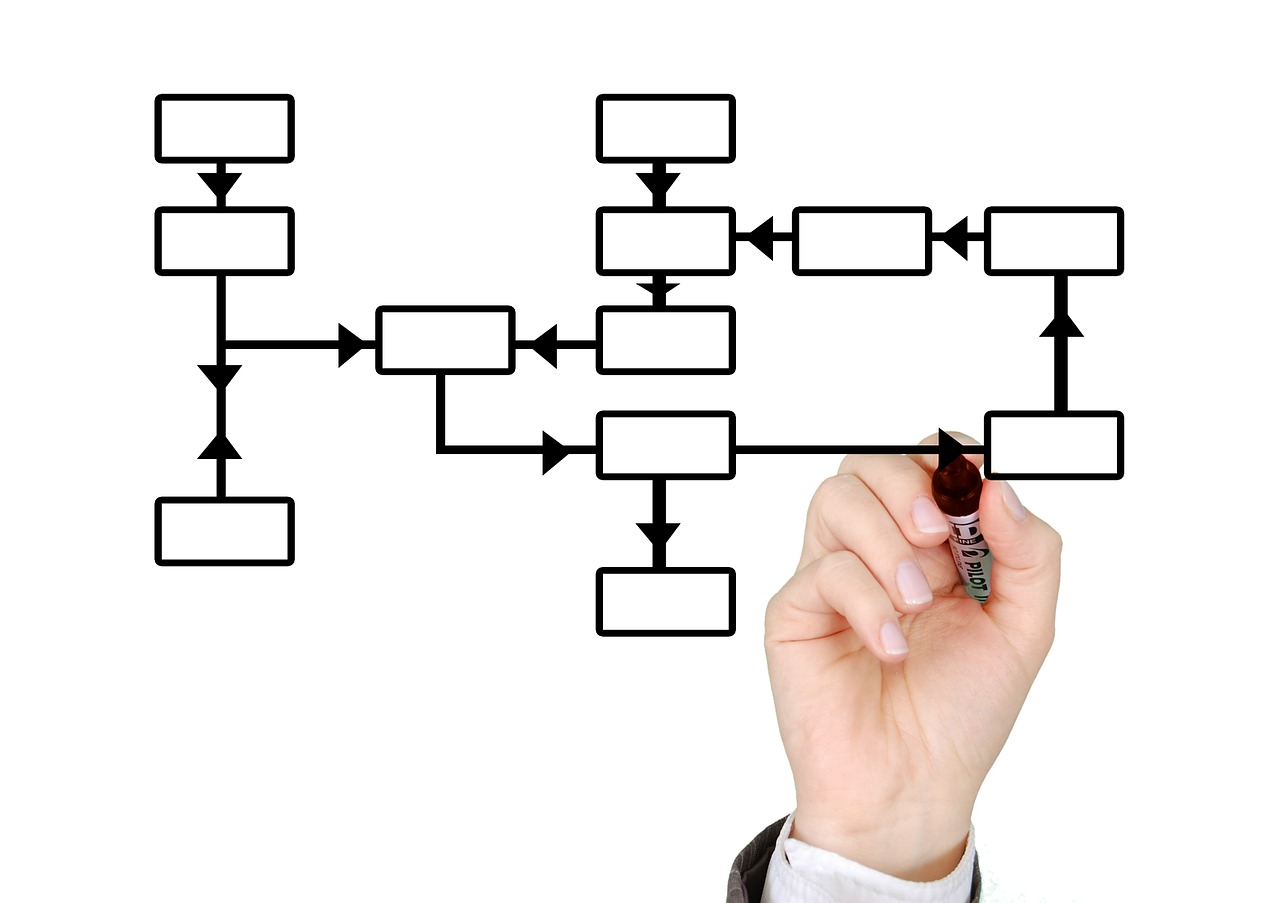筆記試験で最も重要な選択科目Ⅲ。ここで不合格とならないために出題内容や採点項目から解答方法を考えます。日本技術士会が公表した出題内容の重要ポイント5項目、文科省が公表した採点項目と思われる5項目を理解すれば、合格答案の書き方が見えてきます。
選択科目Ⅲの試験概要と重要性
<選択科目Ⅲの試験概要>
試験時間:13:00~16:30(3時間30分の中で自由に選択)
試験内容:選択科目についての問題解決能力及び課題遂行能力に関するもの
出題型式:2問出題1問選択解答、600字×3枚以内
合格基準:配点30点、ⅡとⅢの合計得点(60点)に対し60%以上で合格
評価項目:専門的学識、問題解決、評価、コミュニケーション
選択科目Ⅲの試験は、午後1時から選択科目Ⅱ-1、Ⅱ-2と合わせて行われます。試験問題と答案用紙が一度に配られ、どの問題から解答しても良いことになります。
選択科目Ⅲの配点は30点です。Ⅱ-1の10点、Ⅱ-2の20点と比べても大きな配点ウェイトになっています。さらに、選択科目Ⅲの答案は口頭試験に持ち込まれ、解答内容について質問を受ける場合があります。そこで問題解決や評価の資質能力が不十分と判断されれば、不合格になります。そのため、選択科目Ⅲが午後の試験の中で、最も重視すべき試験であると言えます。
午後の試験時間は3時間半の長丁場ですから、最後は体力的にもきつくなり、思考能力も低下してきます。複数問題を解答する午後の試験は、時間配分を上手く行わなければ、最後に回した問題の解答時間が無くなってしまう場合があります。ですから午後の試験では、体力的にも時間的にも余力のあるうちに、最も重要な選択科目Ⅲの答案を完成させるようにすべきです。
選択科目Ⅲの出題内容と重要ポイントの意味
公表されている選択科目Ⅲの出題内容は以下の通りです。説明文の趣旨を理解してもらうために、重要ポイントとなるアンダーライン箇所の意味を説明していきます。
<選択科目Ⅲの出題内容>
社会的なニーズや技術の進歩に伴う様々な状況において生じているエンジニアリング問題を対象として,「選択科目」に関わる観点から課題の抽出を行い,多様な視点からの分析によって問題解決のための手法を提示して,その遂行方策について提示できるかを問う。
「社会的なニーズや技術の進歩に伴う様々な状況」の意味
これは、社会的ニーズや技術は時間的に変化し、それにより生じる問題を対象に出題するという意味です。インフラに関する問題は、「いかに建設するか」から「いかに維持するか」へと、時代と共に変わってきました。技術の使い方に関する問題も、コンピュータ活用からインターネット活用へ、そしてIoT・AI活用へと変わってきています。つまり、選択科目Ⅲでは、時間的な変化を踏まえた問題解決が求められるということです。
「エンジニアリング問題」の意味
エンジニアリング問題とは、技術士に解決を委ねられる複合的な問題のことです。複合的な問題は、トレードオフ関係にある複数の要因により起こる問題で、時間と共に変化する問題でもあります。例えば、AとBがトレードオフで、Aを犠牲にしてBを優先する解決策を提案したとしても、数十年後には犠牲にしたAのリスクが具現化して、その解決策の有効性は薄れるかもしれないのです。先ほど説明したインフラ問題も、建設するメリットの裏には、将来メンテナンスが増えるデメリットがあります。エンジニアリング問題の解決策には、メリットだけではなくデメリットも必ずあると認識しておくべきです。
「選択科目に関わる観点からの課題」の意味
同じ問題に対して、選択科目によって課題は異なってきます。例えば、豪雨災害に対する問題であれば、河川では洪水氾濫の観点から課題を抽出しますが、道路では交通遮断の観点から課題を抽出します。一方、選択科目は違っても、同じ課題を抽出する場合もあります。例えば、RC構造物の老朽化問題では、河川は河川構造物の観点から長寿命化を課題とし、道路は道路構造物から長寿命化を課題とします。大切なことは、課題を抽出する観点と選択科目の整合です。道路網寸断の観点から堤防強化を課題としても、河川や道路のどちらの科目でも高評価は得られないはずです。
「多様な視点からの分析」の意味
技術士が解決する複合的な問題は、複数要因によるトレードオフ問題です。トレードオフ問題の解決には、問題を発生させる複数の要因を分析して評価しなければなりません。例えば、生産性低下の問題に対して、省力化を課題に挙げる場合、生産性を労働力・生産量・コストから分析します。そのうえで、生産量を優先すべきと評価たことを説明しなければ、労働力を減らす省力化を課題としたことは理解されません。複数要因から分析すれば、おのずと多用な視点から分析していることになります。
「問題解決のための手段及びその遂行方法」の意味
これは、問題解決プロセスを踏んで解決策を提案し、解決策のリスク評価を示すことができるかという意味です。問題解決プロセスとは、①問題特定→②現状把握→③問題点分析(要因分析)→④課題抽出→⑤解決策提案→⑥解決策のリスク評価→⑦リスク対応策(留意点)などの解決手順のことです。選択科目Ⅲの過去問題を見ると、このような7ステップを念頭において作成された問題が多く見られます。問題解決プロセスを踏まえて解答しなければ、重要な資質能力である「問題解決」と「評価」が確認し難くなり、不合格になる確率が高くなると考えておくべきです。
採点項目と確認される資質能力の内容
筆記試験の採点は、解答内容から評価対象の資質能力(コンピテンシー)の有無を確認して行われます。第28回(2018.11.06)技術士分科会・試験部会の配布資料の参考資料7「試験科目別確認項目」では、下表のように資質能力を更に細分化して確認内容が示されています。この表の内容は、受験申込みに関する資料では示されていないことから、筆記試験の採点項目だと考えられます。
| 資質能力 | 必須科目Ⅰ | 選択科目Ⅱ-1 | 選択科目Ⅱ-2 | 選択科目Ⅲ |
| 専門学的知識 | 基本知識理解 | 基本知識理解 | 基本知識理解 | 基本知識理解 |
| - | 基本理解レベル | 業務理解レベル | - | |
| 問題解決 | 課題抽出 | - | - | 課題抽出 |
| 方策提起 | - | - | 方策提起 | |
| 評価 | 新たなリスク | - | - | 新たなリスク |
| 技術者倫理 | 社会的認識 | - | - | - |
| マネジメント | - | - | 遂行手順 | - |
| コミュニケーション | 的確表現 | 的確表現 | 的確表現 | 的確表現 |
| リーダーシップ | - | - | 関係者調整 | - |
次に、選択科目Ⅲ採点項目について、資質能力(コンピテンシー)の要求内容とその意味を考えていきます。
専門学的知識の基本知識理解とは
<要求される資質能力>
技術士が専門とする技術分野(技術部門)の業務に必要な、技術部門全般にわたる専門知識及び選択科目に関する専門知識を理解し応用すること。
選択科目Ⅲで確認される専門知識は、問題解決・課題遂行に必要な知識レベルです。「〇〇について説明せよ」というような知識を問う設問ではなく、問題解決プロセスの説明の中で技術的専門用語が正しく使われているかが確認されます。基本知識理解しか確認しないので、「法令等の制度及び社会・自然条件等に関する専門知識」は評価対象外となります。
問題解決の課題抽出とは
<要求される資質能力>
業務遂行上直面する複合的な問題に対して、これらの内容を明確にし、調査し、これらの背景に潜在する問題発生要因や制約要因を抽出し分析すること。
課題の抽出では、①複合的な問題の内容を明確にしているか、②問題発生要因や制約要因を分析しているかの2点が確認されます。分析をせずに「課題は〇〇である」といきなり課題を挙げると低評価になります。問題の要因を複数分析して、課題を抽出した理由・根拠を示さなければ高評価は得られません。
問題解決の方策提起とは
<要求される資質能力>
複合的な問題に関して、相反する要求事項(必要性、機能性、技術的実現性、安全性、経済性等)、それらによって及ぼされる影響の重要度を考慮した上で、複数の選択肢を提起し、これらを踏まえた解決策を合理的に提案し、又は改善すること。
複合的な問題は、解決プロセスや成果に対する要求事項がトレードオフ関係にあるので、何かを犠牲にしなければ解決策を導き出せません。そのため、各要求事項について犠牲にする場合のリスクを考慮して、いくつか選択肢を検討して解決策を提案することが求められます。例えば、労働時間を減らすと生産量が落ち、生産量確保のために人を増やせばコストがかかります。このようトレードオフ問題に絶対的正解はないので、シミュレーション(複数検討)して最適案を導き出すしかありません。問題解決の方策提起の確認とは、それができるかどうかを確認するということです。
評価の新たなリスクとは
<要求される資質能力>
業務遂行上の各段階における結果、最終的に得られる成果やその波及効果を評価し、次段階や別の業務の改善に資すること。
先に説明した問題解決プロセス(7ステップ)を踏めば、評価(新たなリスク)は見せやすくなります。上記説明文の「業務遂行上の各段階における結果を評価する」とは、問題点分析(要因分析)におけるリスク評価のことで、「最終的に得られる成果を評価する」とは、提案した解決策のリスク評価のことです。「波及効果」には、解決策の有効性に加えて、新たに発生するリスク(デメリット)も含まれます。評価は新たなリスクのみが採点対象ですから、解決策の有効性しか書いていない答案は、評価の資質能力がゼロ点になってしまいます。問題文にも、デメリット、リスク、留意点を書くように指示されるはずです。
コミュニケーションの的確表現とは
<要求される資質能力>
業務履行上、口頭や文書等の方法を通じて、雇用者、上司や同僚、クライアントやユーザー等多様な関係者との間で、明確かつ効果的な意思疎通を行うこと。
試験官が手書き答案を読んで、明確かつ効果的に意思疎通を行えるかということで採点されます。難しい言葉を並べただけで何を言いたいのか理解不能な答案よりも、平易な言葉で内容が理解できる答案の方が、コミュニケーション力は高く評価されます。繰り返しますが、選択科目Ⅲでは問題解決プロセスを伝えなければいけません。それが伝わらない答案は、コミュニケーション能力も低評価になります。
採点項目を踏まえた解答方法
選択科目Ⅲの採点項目と確認される内容が、解答から読み取れれば合格答案になります。試験官が確認したいことは、解決策の是非ではなく、解決策を導き出した過程の是非です。
試験官は、一人で多数の答案を採点しなければなりません。そのため、多くの試験官は、まずタイトルを見てどこに何が書いてあるかを判断するはずです。タイトルをみて確認すべき採点項目が網羅されていないと判断されれば、その答案は不合格グループに振り分けられ、そこでC評価が決定するでしょう。
まずはそうならないように、試験官が確認したい項目が網羅されていることがぱっと見で分かるタイトル構成が必要です。例えば、以下のタイトル構成にすると、問題解決プロセスを踏まえた解答内容だと判判されるでしょう。
1.複合的な問題の特定と現状把握
2.問題発生の要因分析と課題抽出
3.解決策提案とリスク評価・留意点
ここで重要なことは、1.~3.までの内容が全て繋がっていることです。特定した問題の現状を述べたら、その現状から問題発生要因を複数挙げてリスク評価し、優先度を示して課題(対策基本方針)を複数抽出します。課題を抽出したら、課題で示した方針を実現するための解決策を提案し、解決策のリスク評価と留意点を述べます。
本文の内容が、この一連の流れに沿って書かれており、問題解決プロセスやリスク評価に致命的な間違いが無ければ、合格答案グループに振り分けられる確率はかなり高いと思います。一旦A評価となった答案は、よほどのことが無い限りB評価になることはないはずです。