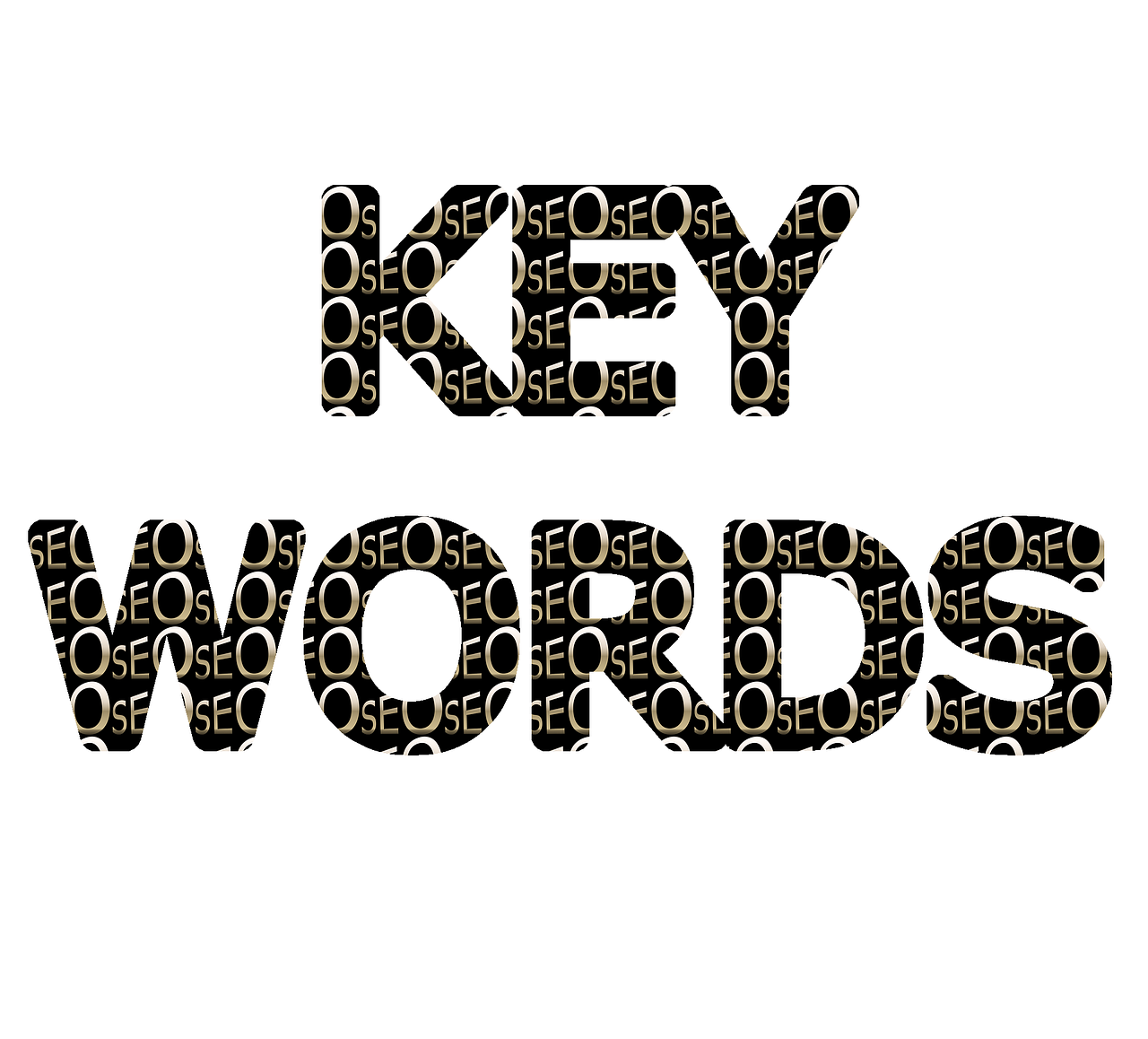2017年、みちびきの打上げ成功で注目される「準天頂衛星システム」。これに関連するワードを4つだけ連想してみると、「衛星測位、GNSS、ドローン、自動運転」が浮かんできました。この4ワードの意味や課題を考え、「準天頂衛星システム」を建設分野の立場から説明してみます。
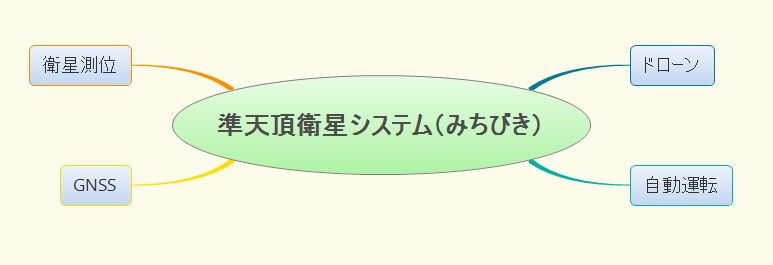
「衛星測位」とは
人工衛星との送受信により、自分の位置やある場所の位置(座標や標高)などを測ることです。位置を知るには、地図や地形図なども必要となります。カーナビやスマホナビは、その両方の機能を持っているので、いま自分がいる場所やこれから行きたい場所の検索ができます。
日本ではアメリカのGPSを使用していましたが、自国のシステムを構築するため、2010年にみちびき1号機を打ち上げ、2017年にみちびき(2~4号機)を打ち上げています。なお、みちびきは単独で測位するのではなく、GPSとの併用で運用し、日本の上空にある衛星の数を増やして測位精度を上げるものです。精度はGPSの10m級から、みちびき4機体制でcm級に向上します。
「GNSS」とは
衛星測位システムの総称のことで、Global Navigation Satellite System ( 汎球測位衛星システム)の頭文字をとってそう呼びます。現在、衛星測位システムは6つあります。
GPS:アメリカ
GLONASS:ロシア
Galileo:欧州連合
BeiDou:中国
IRNSS:インド
QZSS:日本
一般に人工衛星は地球をグルグル回る軌道で飛び、地球の裏側にあるときは送受信できなくなります。しかし、インドのIRNSSと日本のQZSSは、その国の上空を常に網羅するような特殊な軌道で飛びます。そのため、日本のQZSSは準天頂衛星システム(概ね日本の天頂にある)と呼んでいます。
QZSSの衛星は、「みちびき」で現在4機体制(2018年運用開始)となっていますが、2023年には7機体制を目指しています。
「ドローン」とは
無人航空機のことで、UAV(Unmanned aerial vehicle)と呼ぶ場合もあります。建設分野では、空撮、測量、点検等で実用化されつつあり、i-Constructionの進展でドローンによる3D測量が実用化されています。
ドローン測量の課題は、地上に位置の基準となるターゲット(対空標識)の設置への手間と精度でした。しかし、ジャイロセンサー内蔵機種も開発されており、QZSSの精度向上により高精度の3Dレーザー測量が実現しつつあります。
ドローンは、航空機と同様に航空法の適用を受け、また電波法などの規制もあります。今後は、国際民間航空機関(ICAO)による飛行ルールが検討され、操縦士の免許制度も検討されています。
「自動運転」とは
自動車や建設機械の運転を人間の代わりにシステムが行うことです。自動運転には、高度な情報処理、センシング技術、人工知能(AI)を必要とします。
QZSSの精度向上により、自動車の自動運転の実用化が近くなるため、それに対応した道路や駐車場のインフラ整備を進める必要があります。また、CIM対応の建設機械の普及により、ノウハウの少ない地方自治体にもCIMを展開することが今後の課題となります。
自動運転化における課題としては、豪雨時での安全走行や積雪寒冷地における冬期交通への安全走行が挙げられます。
4つのキーワードを用いた準天頂測位システムの説明
準天頂衛星システム(QZSS)とは、日本が構築した汎球測位衛星システム(GNSS)のことであり、日本の人工衛星「みちびき」とGPS衛星を一体とした測位システムです。2018年より「みちびき」が4機体制となり、測位精度がcm級と大幅に向上しました。これにより建設分野では、ドローンによる測量精度や建設機械の自動運転精度が向上し、CIMが一段と進展することとなります。今後は、ドローン飛行に関する法制度整備、開発が進む自動車の自動運転に対応する道路インフラ整備が課題と考えます。