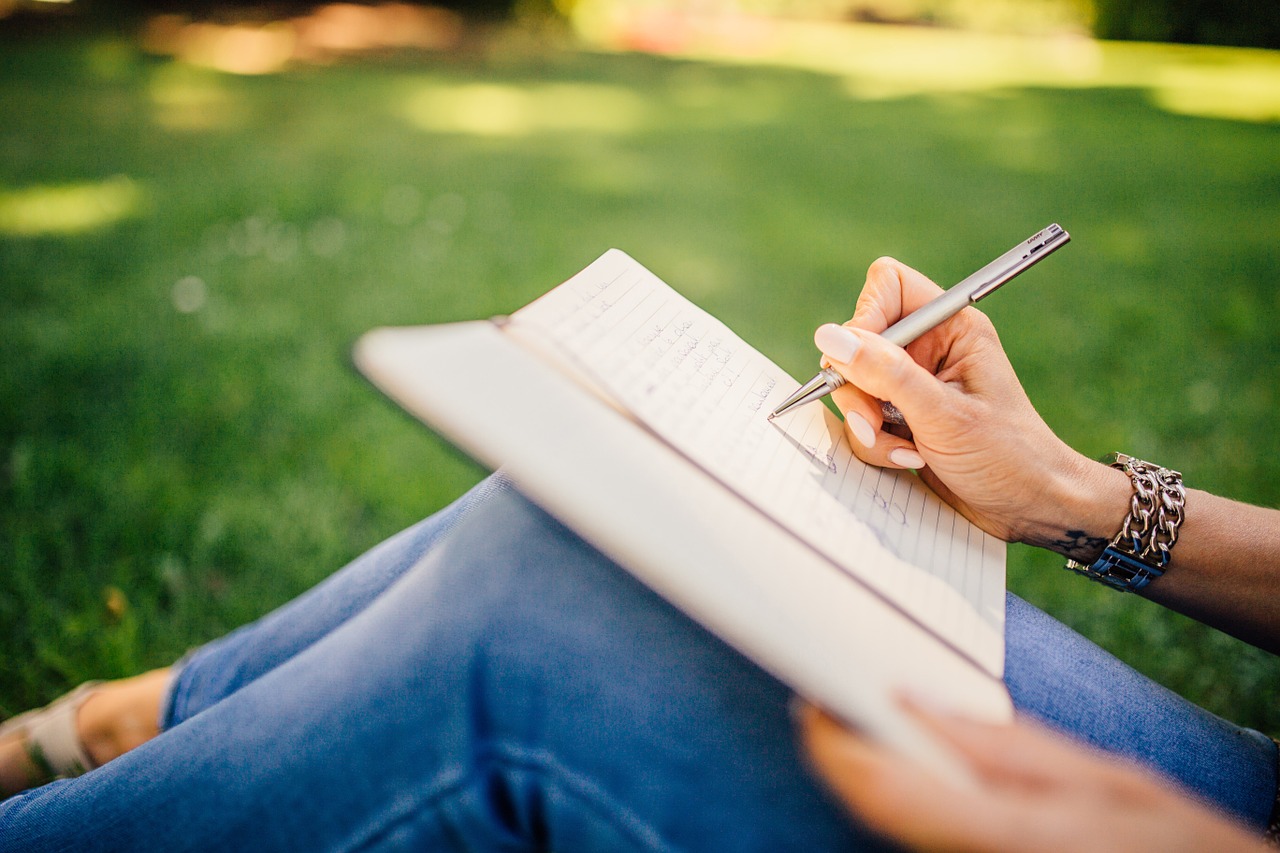受験申込書作成で一番悩むのが、720文字の業務詳細ではないでしょうか。技術的内容を書けば良いのか、それとも口頭試験で質問される4つのコンピテンシーをアピールすべきか迷う人も多いと思います。今回は、業務詳細の書き方について説明したいと思います。
業務詳細に書くべき業務とは
業務詳細の書き方を迷う原因は、何を書くべきかの説明が2つ存在するからです。1つ目は技術士法、2つ目は「今後の技術士制度の在り方について」です。2019年度から始まった新試験制度は、「今後の技術士制度の在り方について」の内容に沿ったもので、国際エンジニア連合(IEA)が2009年に定めたプロフェッショナル・エンジニアのコンピテンシーレベルを確認する試験です。
技術士法は1957年に作られた法律で、制定当初から「高等の専門的応用能力・・・」という技術士の定義は変わっていません。これまで「専門的応用能力」の統一した概念が示されていなかったため、高等かどうかの判断は人それぞれ異なっていました。つまり技術士法では、技術士の資質能力レベルが曖昧だったということです。一方、IEAが定めるコンピテンシーは、文章で定義づけされています。新制度試験で確認される「技術士に求められる資質能力(コンピテンシー)」も、原文を翻訳して設定されたものです。
日本技術士会としては、技術士法を無視して説明できないので、業務詳細に書くべき事項は、技術士法に従って「専門的応用能力・・・」を書くよう指定せざるを得ません。しかし、その業務詳細を使って口頭試験で確認されるコンピテンシーは、「今後の技術士制度の在り方について」で設定された「複合的な問題」を解決できるレベルです。
したがって、業務詳細に書くべき業務とは、複合的な問題を解決した業務でなければなりません。そうでなければ、技術士にふさわしいコンピテンシーレベルが伝わらないということです。
業務詳細で意識すべきコンピテンシー
「今後の技術士制度の在り方について」では、口頭試験の確認内容を次の4項目としています。
<口頭試験の確認内容>
(1)技術士として倫理的に行動できること
(2)多様な関係者と明確かつ効果的に意思疎通し、多様な利害を調整できること
(3)問題解決能力・課題遂行能力:筆記試験において問うものに加えて、実務の中で複合的な問題についての調査・分析及び解決のための課題を遂行した経験等
(4)これまでの技術士となるための初期の能力開発(IPD)に対する取組姿勢や今後の継続研さん(CPD)に対する基本的な理解
(3)の下線部分は、「問題解決」のコンピテンシーと同様の内容です。複合的な問題の解決能力は、新制度試験の目的でもあり、技術士が備えるべき最も重要な能力と位置付けています。口頭試験はその実務能力を最終確認する場です。
<「問題解決」のコンピテンシー>
・業務遂行上直面する複合的な問題に対して、これらの内容を明確にし、調査し、これらの背景に潜在する問題発生要因や制約要因を抽出し分析すること。
・複合的な問題に関して、相反する要求事項(必要性、機能性、技術的実現性、安全性、経済性等)、それらによって及ぼされる影響の重要度を考慮した上で、複数の選択肢を提起し、これらを踏まえた解決策を合理的に提案し、又は改善すること。
業務経歴票を基に確認するコンピテンシーは、コミュニケーション、リーダーシップ、評価、マネジメントの4つと公表されています。しかし、これらの質問は、問題解決プロセスの妥当性を判断するためと考えるべきです。
コンピテンシーに関する質問を意識して、業務詳細の内容を意思疎通、利害調整、結果評価、資源配分などの業務管理的な内容にしてしまうと、肝心の問題解決能力が読み取れなくなってしまいます。そうなると、問題解決能力・課題遂行能力が文章からは確認できないので、口頭試験で問題解決に関する技術的な質問が多くなると思われます。口頭試験は、限られた時間の中で行われますから、技術的な質問に時間を費やすと、評価対象コンピテンシーを確認する時間が無くなり、不合格となる可能性が高まります。
業務内容の詳細では、「問題解決」のコンピテンシーを意識して、複合的な問題の解決プロセスを書くようにします。そうすれば、コミュニケーション、リーダーシップ、評価、マネジメントを発揮して問題解決したことが、自ずと伝わるようになります。
試験官が理解しやすい業務を選ぶ方法
業務詳細に書く業務を「難しいことをやった。一番苦労した」という基準で選ぶ人もいますが、複合的な問題の解決が伝わらなければまったく意味がありません。試験官は、業務の難易度や苦労話に対して採点するわけではなく、問題解決に発揮したコンピテンシーに対して採点します。ですから、業務詳細に書く業務は、試験官が複合的な問題の解決ストーリーを理解しやすい業務から選んだ方が良い結果につながります。
複合的な問題は、適切なプロセスを踏まなければ解決できない問題です。その適切なプロセスは、①目標設定→②現状把握→③問題分析→④課題設定→⑤対策立案→⑥対策実施→⑦結果評価の7ステップとするのが良いと思います。
そうすれば、試験官が業務詳細から読み取る次の3ポイントが伝わりやすくなります。
試験官が業務内容の詳細から読み取るポイント
ポイント1:複合的な問題の解決ストーリー
ポイント2:問題解決過程の思考プロセス
ポイント3:解決策の効果・リスク・改善策
また、試験官が理解しやすい複合的な問題の解決ストーリーは次の3パターンなので、どれかのパターンにはまる業務を選定するのが良いと思います。
解決ストーリーが理解しやすい3パターン
パターン1:一般的方法を工夫・改善して有効化した
パターン2:マニュアルが無い課題を合理的に解決した
パターン3:トレードオフの折合い点を倫理的に提案した
業務詳細のタイトル構成と本文内容
「今後の技術士制度の在り方について」では、業務経歴票に「業務の内容、業務上での問題や課題、技術的な提案や成果、評価及び今後の展望」の記載を求めるとしています。業務詳細のタイトルはそれに合わせて4タイトルが良いと思います。
各タイトル構成の内容は、先に示した問題解決7ステップに基づき思考プロセスが見えるように書きます。
技術士にふさわしい業務に見せようとして、たくさんの要求事項、難しい技術、最新工法などを書き並べたくなるかもしれません。しかし、試験官が確認したいのはそのような内容ではなく、あなたが普段どのような考えで問題を解決しているかです。あなたの思考プロセスが技術士にふさわしいものなら、今後さらに難しい複合的な問題に直面しても、きっと同じような思考プロセスで解決できるだろうと判断してくれます。思考プロセスを見せることは、あなたのコンピテンシーを見せることでもあるのです。