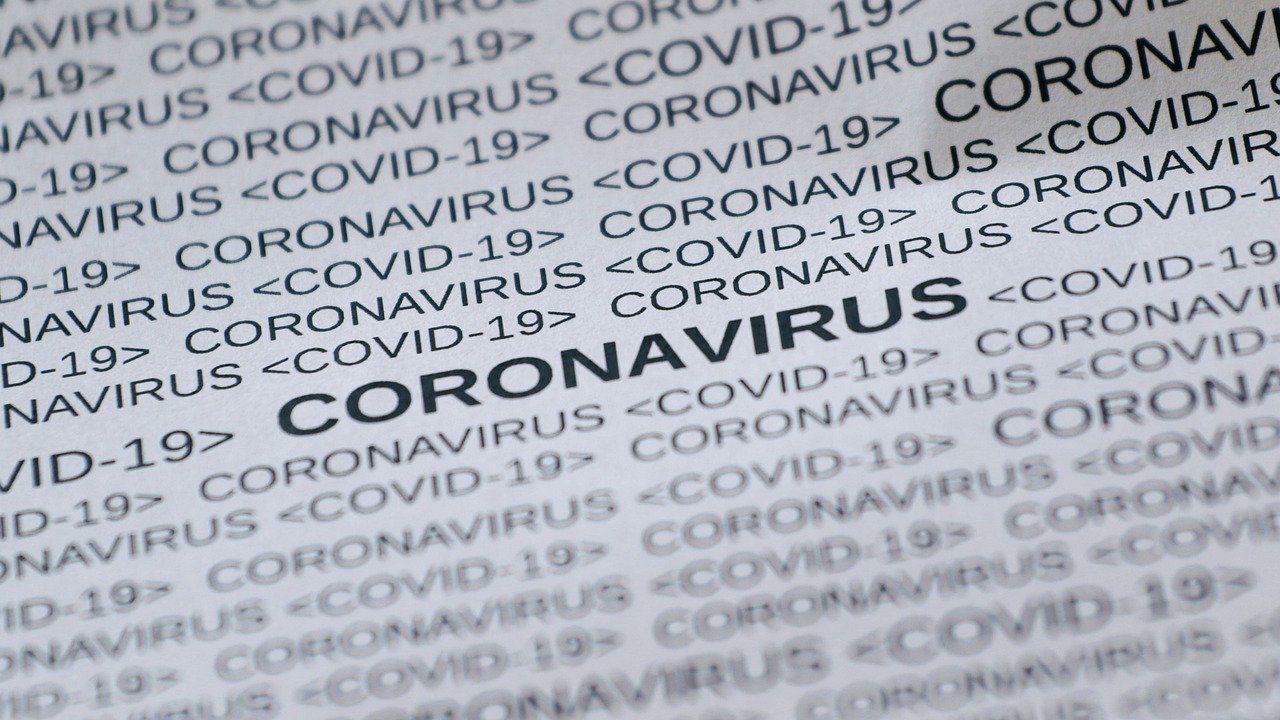日本技術士会HPに令和2年度の第二次試験の問題文が掲載されています。一般6部門と総監で新型コロナを意識した問題文が見られます。中には意図的に触れないようにした問題文も。今回は、新型コロナの影響の大きさを筆記試験の試験問題文から考えてみます。
一般6部門で新型コロナの影響を意識した問題が出題
公表された問題文をざっと見たところ、衛生工学、化学、機械、電気電子、経営工学、金属の6部門で、新型コロナの影響を意識した問題を確認できました。
衛生工学部門の必須科目Ⅰ-1では、以下のような前文が示され、街区スケールでの感染拡大防止をテーマとした問題が出題されています。
2019年12月以降,世界中で「新型コロナウイルス感染症」の感染拡大が問題となっている。感染拡大防止を目的とした法律として「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」「検疫法」などがあり,「新型コロナウイルス感染症」も同法の指定 感染症に定められている。その一方で,感染拡大防止のためには法令等による社会制度で取り組む対策から,民間組織,個人が取り組む対策まで多様な取組が考えられ,我が国においても感染拡大防止の観点から,多くの社会活動が制限・自粛されるなど,経済活動にも大きな支障が出ている
他にも、化学部門Ⅰ-1の前文には、「世界的な感染症の流行」と書かれていて、新型コロナを意識した問題文となっています。さらに、選択科目でも機械-加工・生産システム・産業機械Ⅲ-1には「感染症の流行」、電気電子-情報通信Ⅲ-には「パンデミック」、経営工学-サービスマネジメントⅡ-2-2には「新型ウィルス蔓延」のワードが使われ、新型コロナの影響が伺われます。
私が注目したのは、金属部門-金属加工Ⅲ-2の問題です。作問時期が緊急事態宣言期間中とはいえ、テレワークをテーマとした出題は無いと思っていましたから、ここまでズバリの問題が出たことには驚きました。
テレワークとは, 「ICT(情報通信技術)を活用し,時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方」であり,導入が呼びかけられていたが,製造業においては浸透していないのが現状であった。2019年の年末頃よりはじまった感染症の拡大は世界の様相を一変させた。下記の内容を記述せよ。
(1)金属加工分野におけるテレワークの取組(緊急事態に限定しない)を技術士の立場として多面的な観点からその方法や課題を抽出し分析せよ。
(2) 抽出した課題において重要と考えた課題及びその解決策を述べよ。
(3) 解決策により新たに生じうるリスクとそれへの対策について述べよ。
テレワークにおける記述的課題は、他分野でも広く問われておかしくない問題です。来年は、このような出題を多くの受験者が想定することになるかもしれません。
河川砂防Ⅲは複合災害に触れないよう配慮した問題か
昨年の台風19号による大規模水害の発生をうけて、国はこれまでのあふれさせない治水から、あふれることを許容する流域治水に舵を切ったばかりです。このパラダイムシフトは、河川砂防分野にとっては大きな出来事でした。
多くの受験者は、選択科目Ⅲで水災害関連のテーマが出題されると予想していたと思います。私自身も、河川砂防Ⅲは水災害が本命テーマと想定して添削指導を行ってきました。
しかし、蓋を開けてみればデータプラットフォームの実現と総合的な土砂管理です。受験者はもちろん、指導者の中にも、この問題に違和感を覚えた人は多かったのではないでしょうか。
なぜこの2つが河川砂防Ⅲのテーマになったのか、その理由を少し考えてみます。
4月に公表した受験申込の案内には、自然災害による試験中止の判断基準が示され、自然災害の定義が被害者生活再建支援法に基づき示されていました。被害者生活再建支援法の定義では、新型コロナのような感染症は自然災害に含まれていません。その後も技術士会のHPで、この法律で定義する自然災害以外は、試験を中止しないことをアナウンスしていました。
コロナ禍において水災害の問題解決を問われれば、自然災害と新型コロナの複合災害に対して、課題や解決策、派生リスクを解答する答案が多くなることが予想されます。今回は、この複合災害対応がテーマと捉えられないよう配慮したのかもしれません。
考えすぎかもしれませんが、複合災害に新型コロナを含める考えに対して合否を判定することは、新型コロナも自然災害の一つであるということを認めることにつながりかねません。
7月の九州豪雨でも複合災害は話題となり、新型コロナでの生活支援に被害者生活再建支援法の適用を訴える声も一部で上がっていました。また、大規模自然災害と同様に新型コロナ感染拡大により、筆記試験を中止すべきとの声も多数上っていました。そのため、新型コロナを自然災害とすべきか否かについては、文科省や技術士会も敏感になっていたと思います。
このような背景から、新型コロナを自然災害と認めるような問題は、あえて避けたように思えるのです。そうは言っても、完全回避もあからさますぎるので、Ⅱ-2はいずれも災害関連の問題にしたのかもしれません。
総合技術管理では自然災害から感染症は除外の一文も
総監の記述問題Ⅰ-2は、事業場における異常な自然現象へのリスク対応がテーマでした。問題文の設問(2)で、異常な自然現象を定義しているのですが、その最後にシンボリックな一文が書かれています。
(2)問い(1)で取り上げた事業場に対して,将来,甚大な被害を及ぼす可能性のある異常な自然現象を1つ選び,それによる主要な被害やそれらに備えた対策について,次の①,②に沿って示せ。ここでの「異常な自然現象」としては,暴風,豪雨,豪雪,洪水,高潮,地震,津波,噴火,又は台風のようにそれらが複合したもの,とする。
感染症の流行は,ここでの異常な自然現象には含めない。
この一文に衝撃を受けた受験生もいたようです。これからの総監技術士には、自然災害と新型コロナの複合リスクのマネジメントが絶対必要になると考えて、これまで勉強してきた人にとっては、「なんで!」という気持ちにだったのでしょう。
ここでも、文科省や技術士会は、新型コロナを自然災害に含めることを容認しない姿勢が伺えます。今後、法解釈や法改正があるかもしれませんが、来年以降の試験で新型コロナを自然災害とする解答をした場合、どのように判定されるのかを考えておく必要がありそうです。
口頭試験に向けて新型コロナ対策の法的整理を
今年の筆記試験の合格発表は、令和3年1月8日です。この時期に、新型コロナがどのような状況になっているかはわかりません。しかし、基本的に新型コロナで口頭試験が中止になることは、法的にもないと思います。
口頭試験では、必須科目Ⅰや選択科目Ⅲの解答内容について質問される可能性があります。もし、コロナ禍における災害対応について解答で触れているなら、その考えを問われかねません。少なくとも、自然災害と新型コロナの同時発生について、自分なりに法的整理をしておく必要がありそうです。
国と自治体では法体系も違うでしょうし、技術部門によっても違うでしょう。正解は無いのかもしれませんが、建設部門の災害対策と他部門の衛生対策では、法的位置づけも違うでしょうから、口頭試験では、その辺をしっかり踏まえて回答する必要がありそうです。
私もまだ勉強不足なのですが、今回の筆記試験問題を見る限り、自然災害対策は災害対策基本法、新型コロナ対策はその他の基本法の下で解決策を導出することが、技術士には求められているように思いました。つまり、建設部門の技術士が防災対策を提案する際には、新型コロナを自然災害に含めないで考えるということです。
技術者倫理として、それで良いのかと思うところもありますが、他の技術分野との連携強化の必要性がより強く求められるのかもしれません。
最後に、私自身いろいろ想定問題を作っていたのですが、新型コロナの影響を読み切れなかったこともあり、今回は結構外しまくりでした。口頭試験や次年度試験に向けて、新型コロナの影響を踏まえた有効なアドバイスができるように、さらに勉強していきたいと考えています。