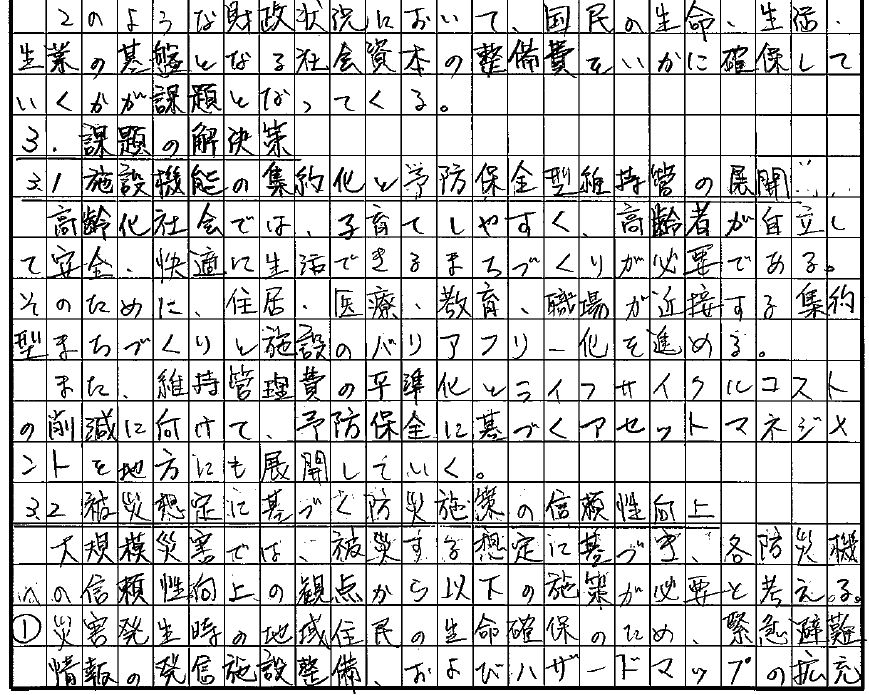筆記試験の模擬答案をワープロで作成している人は多いと思います。しかし、筆記試験本番では手書きで解答しなければなりません。手書きでは、ワープロなら当然できたことができなくなることがあります。私が実際に体験した、手書き答案で困った「手書きあるある」をいくつか紹介します。
すごく簡単な漢字が書けなくなり、屈辱感に打ちひしがれる
私にとっては、漢字の書き取りが一番の悩みでした。以前、「燃焼」の「燃」という漢字がどうしても思い出せず、後で思い出せるだろうと1マス空けて書き進んだのですが、とうとう時間切れとなり、空けておいた1マスにカタカナで「ネン」の2文字を書いたことがあります。それでも合格したのですが、その時の屈辱感というか、敗北感は今でも忘れることができません。
それ以外にも、猛威、拍車、汚濁、避難、警戒など、漢字が書けずに屈辱のカタカナ書きは、これまで多々あります。ちなみに、カタカナで書くのは、「ちょっと度忘れ」感を出すためです。あまり効果はないでしょうけど、ひらがなよりはマシかと思っています。
漢字が苦手な私は、試験前には小学生のように漢字の書き取り練習をします。これくらいの漢字は書けるでしょうと、高をくくっていると思わぬところで痛い目に合いますので、くれぐれもご注意ください。
スペルチェックも変換リストも無いので、間違いに気づかない
Wordなどにはスペルチェック機能があるので、日本語の間違い箇所は、赤いアンダーラインが出てすぐに分かります。しかし、手書きではそのような機能は使えないため、自分でチェックするしかありません。試験本番では時間的余裕もないので、間違いに気づかないこともあるはずです。
特に何度も消したり書いたりをくり返すと、消し忘れや書き忘れもあって、後で読み返すと意味不明な文章になっていることもあり、修正に手間取ってしまいます。
また、ワープロでは当たり前の変換リストも出てこないので、正しい漢字がどっちかで迷ったり、正しい送り仮名が書けないこともよくあります。「改める」「確かめる」などは、ワープロなら気にもしませんが、手書きとなると「め」を書くかどうか迷ってしまうのは、きっと私だけではないと思います。
手書きの模擬答案を誰かに添削してもらうのが、間違いに気付く一番良い方法です。私の経験では、専門が違う大ベテランに見せるのが、日本語の使い方しか指摘してこないので有効だと思います。
辞書機能が使えず、単位やアルファベットの大文字・小文字で迷う
普段使っているワープロには、辞書登録機能が付いているので、よく使う単位(MPa、kN、kgf、pHなど)はあらかじめ登録してあります。なので、普段は何も考えずに単位を書いているのですが、これが手書きとなると大文字か小文字かで迷ってしまうことがあります。
私の経験では、メガパスカル(MPa)を書くとき、Mは大文字、aは小文字は分かっていたのですが、真中のPが大文字だったか小文字だったか迷ったことがあります。Pを手書きすると、大文字も小文字も同じような書体になるので、どうでもよかったのですが、意外と盲点だと思いました。
そもそも手書きの場合、アルファベット小文字はブロック体なのか筆記体なのかさえも分からず、迷う人もいると思います。基本はブロック体で書くのですが、慣れないとブロック体は意外と書きにくいです。
最近なら少なくとも「i-Construction」は、ブロック体で手書きできないと困るでしょう。書体よりスペルを間違う方が恥ずかしいので、そこはしっかり練習しておくべきです。
DeleteやBack-Spaceキーが無く、消しゴムで辛い思いをする
ワープロ書きでは、DeleteやBack-Spaceキーがあるので、削除が簡単にできます。でも、手書きでの削除は、全て消しゴムを駆使しなければいけません。電動消しゴムも字消し版も使えないので、かなり辛い思いをするはずです。
ワープロならDeleteやBack-Spaceキーを押して消してしまえば、文字をずらしてくれるので、あっという間に修正できるのですが、手書きは1文字追加するのも大変です。まして、1フレーズ入れたいと思えば、前後の行まで消して、必要文字数のマス目を空けなくてはいけません。
逆に1フレーズ削除するのも大変な作業で、中途半端な空白ができるので、それを埋めるために余計な言葉を書き足さなくてはいけなくなります。終了間際にマズイ箇所を見つけても、修正時間が無くて泣く泣く諦めることもあるでしょう。
普段何気なく使っているDeleteやBack-Spaceキーが、いかに便利な機能かが、手書きでは実感できます。試験本番までに、DeleteやBack-Spaceキーを使えないことに慣れておくべきだと思います。
消しゴムを駆使するために、どんな消しゴムが自分に合うか、事前に確認しておくことは必要だと思います。なお、消しゴムを使う練習もしっかりやっておくべきです。
タイトルにアンダーラインを引く時、失敗しないように気を使う
私のように字が汚いと、手書きの場合はタイトルと本文の区別がつきにくくなります。もちろん、タイトルには”1.”や”(1)”などの番号を振りますが、それでもワープロに比べて区別が付きにくくなります。そのため、私はタイトルに必ずアンダーラインを引くようにしてきました。
ワープロならクリックすればアンダーラインを引いてくれます。失敗しても、「元に戻す」をクリックすれば良いわけです。しかし、手書きの場合は定規を当てて、線を引かなければなりません。失敗するとアンダーラインだけ消すのは至難の業で、文字も一緒に消して書き直すことになります。
ちなみに、私は2Bの濃いめのペンシルでガッツリ書くので、長いタイトルならアンダーラインを引かないと、本文と同化して区別し難くなります。白黒コピーだと、マス目の線もあるので、アンダーラインはマス目の線を外すようにしています。
おわりに
いかがでしたか、同じ思いをした方もいるのではないでしょうか。試験官だってワープロ世代ですから、昔ほど手書き原稿の書き方にうるさく無いように思います。とわ言え、ぶっつけ本番でいきなり手書きは危険なので、本番前に一度は手書き練習をして「手書きあるある」を体験しておくことをお勧めします。