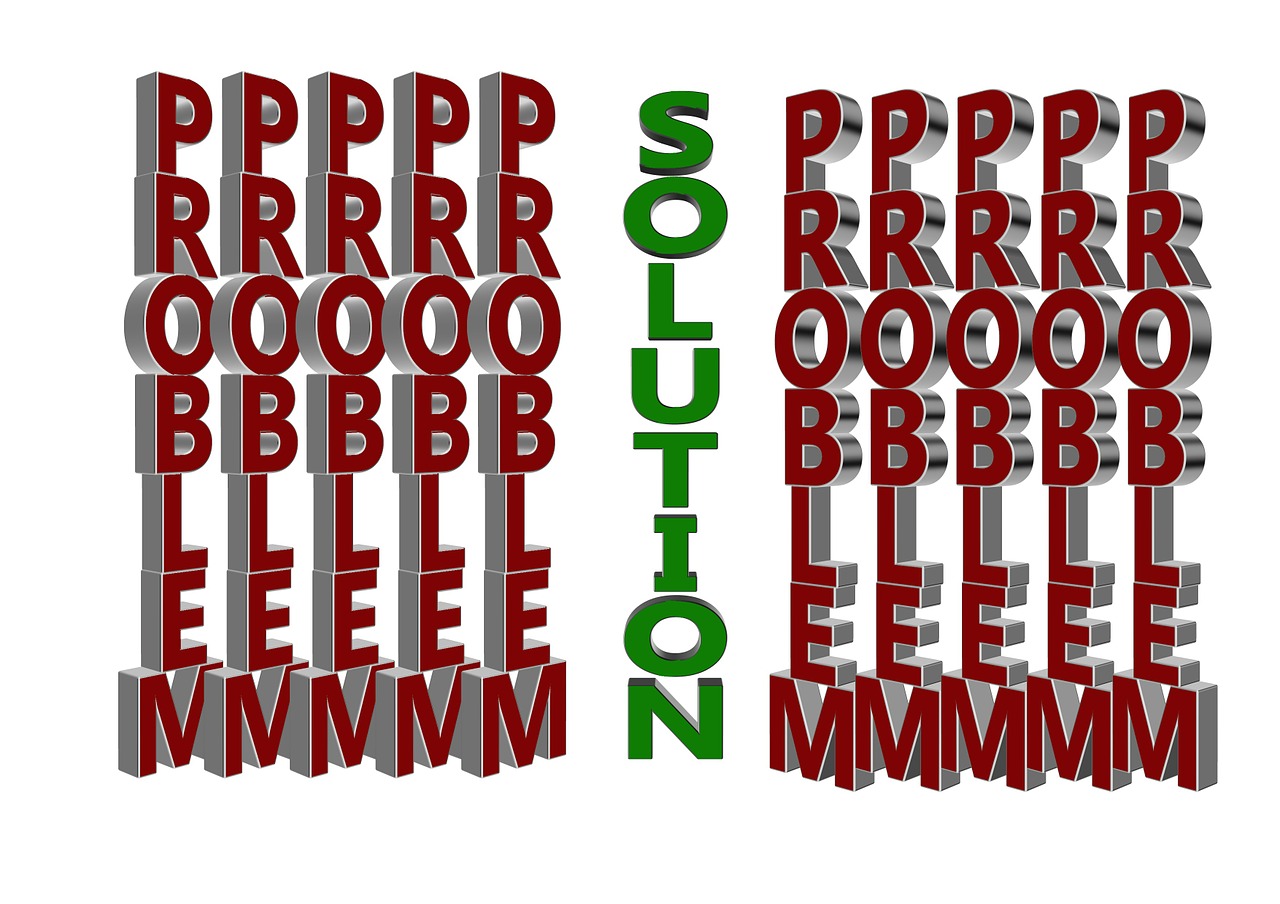技術士には複合的なエンジニアリング問題を解決する役割があります。最近耳にする複合的とは何なのか?技術士試験でも、その理解度が重要なポイントになりそうです。私も技術士として仕事を続けるため、複合的の意味を考え、自分なりの解釈で整理してみました。
「複合的な問題」は技術士試験の重要キーワード
2016年12月に文科省から公表された「今後の技術士制度の在り方について」では、技術士像として「複合的なエンジニアリング問題を解決する技術者」をイメージしています。
また、技術士コンピテンシーの説明や、二次試験の「問題解決能力及び課題遂行能力」の概念にも「複合的な問題」というワードを使っています。
このように、技術士試験はもちろん、技術士として仕事をする上でも「複合的な問題」が極めて重要なキーワードになっています。
「複合的な問題」の意味を知らずして技術士合格なし、そう言っても過言ではないでしょう。
文科省の定義がザックリ過ぎて具体的イメージがわかない
「複合的な問題」の定義を探して見ると、意外と書かれているものが少ないのが現状です。
それでも、「今後の技術士制度の在り方について」の別紙5、「今後の技術士二次試験の在り方について」の中で次のように書かれており、これがオーソライズされた定義になっています。
「複合的な問題とは、広範囲な又は相対立する問題を含み、その問題を把握する時点において明白な解決策がなく、様々な面において重大な結果をもたらすものである」
なんとなく分かるのですが、ザックリ過ぎて具体的なイメージがわかないのも事実です。
受験申込み時の業務経歴書の詳述業務には、ここに書いてあるような複合的な問題を解決した業務を書きましょうと言っても、どんな業務を書けば良いのか、分からないと思います。
「明白な解決策が無い業務経験が無ければ技術士になれないのでしょうか?」
そう質問してくる受験者もいるのではないでしょうか?
IEAの定義はアカデミック過ぎて難しい
文科省がイメージする技術士像は、国際エンジニアリング連合(IEA)が定める「Graduate Attributes and Professional Competencie(GA&PC)」をベースにしています。JABEEのレベルもこれがベースになっています。
GA&PCは英語で書かれていますが、文科省ではこれを日本語に翻訳して、技術士制度の議論に使ってきました。ちなみに翻訳版と原文が、文科省の「第7期技術士分科会制度検討特別委員会(第11回)」の配付資料からダウンロードできます
複合的な問題の定義は、GA&PCの4.1に書かれていています。以下翻訳版から抜粋したものです。
【複合的な問題(Complex Problems)】IEA-GA&PCより抜粋
- 定義:多くが専門分野の最先端にある、又はその情報に基づく広く深いエンジニアリング知識なくしては解決し得ない、以下の特性のいくつか又は全てを有するエンジニアリング問題
- 要求事項相互間の矛盾の程度:広範囲な又は相対立する、テクニカルな問題、エンジニアリング問題、及び他の問題を含んでいる
- 求められる分析の深さ:明白な解決策がなく、適切なモデルを考案するための解析に、抽象的思考と独創性が求められる
- 求められる知識の深さ:多くが専門分野の最先端にある又はその情報に基づく、そして、基本に帰り原理に立った分析アプローチを可能にする研究ベースの知識を必要とする
- 問題に対する熟知度:めったには直面しない問題を含んでいる
- 基準適用の可能性:専門職のエンジニアリング活動の基準や規範で成し遂げられる問題の範囲を超えている
- 利害関係者の関与範囲と、それぞれの要求の合判度合:広く異なる要求を有する多様な利害関係者の集団を含む
- 結果:様々な面で重大な結果をもたらす
- 相互依存性:多くの構成要素又は下位の問題を含むハイレベルな問題である
赤文字のフレーズを繋ぐと、先ほどの文科省のザックリ定義になるのが分かります。
いろいろ書いてありますが、アカデミック過ぎて理解するのが難しいと感じるのは、私だけではないと思います。
自分なりの解釈でIEA定義を整理してみた
IEAの定義がわかり難いので、自分なりに解釈して整理してみました。
複合的な問題とは、次の8つの問題が複数含まれる問題と捉えれば良いのではないかと思うのです。
①複数の要因が絡む問題
②トレードオフの解決が必要な問題
③重大なリスクを含む問題
④標準的手法で解決できない問題
⑤解決マニュアルが無い問題
⑥極めて稀な事象を含む問題
⑦利害関係者の調整が必要な問題
⑧複数の専門技術が必要となる問題
この内、最も重要なのが①②③、次に重要なのが④⑤だと思います。業務経歴票の作成に向けては、①~⑤の問題を含む業務経験を洗い出して見ると良いと思います。⑥⑦⑧は、あまり意識し過ぎない方が良いかもしれません。
まずは、複数要因・トレードオフ・重大リスクの3つを考える
複数要因・トレードオフ・重大リスクの3つの問題を考えれば、複合的な問題を解決した業務は、意外と簡単に見つかります。
複数要因とトレードオフは、どんな業務にも多かれ少なかれ含まれていると思います。品質・コスト・納期だけでも3つの要因がトレードオフ関係になるはずです。
そして、それを解決しなければ重大な結果につながる、すなわち重大リスクを含む業務を考えます。
重大リスクとは、公益を考えるとわかりやすいです。エンドユーザーの安全が脅かされ、不利益を受けるリスクは重大リスクですし、環境の保全が脅かされるのも重大リスクです。
例えば、コストを抑えると安全基準が確保できないリスクは重大リスクになります。コストを優先して品質改ざんした結果、大事故や健康被害を起した会社で考えるとわかりやすいかもしれません。
問題の要因が複数あるということは、問題の範囲が広いということ、トレードオフは問題が相対立するということ、重大リスクは重大な結果をもたらすということです。それにトレードオフやリスク対策に絶対的な答えはありません。つまり明白な解決策がないということです。
そう考えると文科省の定義の意味も少し見えてくるのではないでしょうか。
「複合的な問題とは、広範囲な(複数要因が絡む)又は相対立する問題(トレードオフ)を含み、その問題を把握する時点において明白な解決策がなく(絶対的正解がなく)、様々な面において重大な結果をもたらす(重大リスクを含む)ものである」
「明白な解決策がなく」の真意を深堀りしてみる
複数要因が絡むトレードオフ問題は、解決策は一つではなく複数あるということです。さらに複数要因が絡むということは、問題や解決策の有効性も時間や環境の変化で変わるということにもなります。
例えば、現在はインフラ維持管理が大問題ですが、建設当時は経済成長の基盤整備の方が大問題だったわけで、インフラは維持管理よりも整備が優先されていました。つまり、インフラの問題は時間と共に変化し、その時の状況に応じて解決策の有効性は変わってきたということです。
すなわち、複合的な問題の解決策には絶対的な答えが一つあるのではなく、時間と環境により解決策の有効性は変化すると言うことです。
文科省の定義に「その問題を把握する時点において明白な解決策がなく」とわざわざ時間的要素を書き加えて、明白な解決策(絶対的な正解)はないとしているのは、複合的な問題にはそういう特徴があるからなのでしょう。
問題解決・課題遂行能力の概念も理解しやすくなる
複合的な問題の意味が理解できたなら、筆記試験で試される問題解決・課題遂行能力の概念を見てみましょう。
社会的なニーズや技術の進歩に伴い,社会や技術における様々な状況から,複合的な問題や課題を把握し,社会的利益や技術的優位性などの多様な視点からの調査・分析を経て,問題解決のための課題とその遂行について論理的かつ合理的に説明できる能力
複数要因・トレードオフ・重大リスクを把握するために調査・分析は必要です。しかも、明白な答えはないので、社会的利益や技術的優位性などの多様な視点から調査・分析をしなければなりません。
問題が明らかになれば、それを解決する方向性を定める必要があります。それが課題の抽出になります。課題が抽出できれば、解決策を示すのはそれほど難しいことではありません。
筆記試験では、問題文で与えられたテーマについて、複合的な問題と捉えて課題を抽出できるかどうかがポイントになりそうです。
最後にエンジニアリングとは何かを知る
ここまでは複合的な問題について考えてきましたが、最後にエンジニアリングとは何かを考えてみたいと思います。
IEA-GA&PCの序文で、エンジニアリングのことについて次のように書かれています。
1序文・・・IEA-GA&PCより抜粋
エンジニアリングとは、人々の必要を満たし、経済を発展させ、また、社会にサービスを提供するために不可欠な活動である。エンジニアリング活動には、数学、自然科学、及びエンジニアリング知識、テクノロジー、並びにテクニックの体系の合目的応用が含まれる。エンジニアリング活動には、しばしば不確定な状況の下で、その効果が最大限得られると予想される解決策を生み出すことが求められる。エンジニアリング活動は、便益をもたらす一方で、負の結果をもたらす可能性がある。それ故、エンジニアリング活動は、責任を持って、倫理的に、また、利用可能資源を効率的に使用しながら、経済的に、健康と安全を守りつつ、環境面で健全かつ持続可能な方法で、そのシステムが作られてから廃棄されるまでの全体にわたってリスクを全般的に管理しながら行われなければならない。
この文章、技術士(プロフェッショナル・エンジニア)が果たすべき役割を的確に表現しているのではないでしょうか。口頭試験で「技術士とはどういう人だと思いますか?」と質問された時、回答に思わず使いたくなるフレーズが満載です。
エンジニアリングとは、技術士としての活動のことであり、科学技術が持つ良い面と悪い面を常に考えながら、公益確保を最優先にして最適な解決策を提供する活動だと解釈できそうです。
まとめ
複合的なエンジニアリング問題を、私なりに解釈するとこうなりました。
「複数要因が絡みトレードオフや重大リスクが含まれ、技術士に解決を託すべき問題」
皆さんも、技術士が解決する複合的なエンジニアリング問題とは何かを、自分なりに整理して見てはどうでしょう。技術士への理解が、より深まると思います。