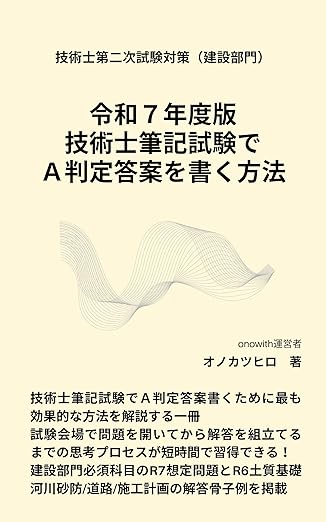建設部門必須科目Ⅰの過去6年の出題傾向を分析し、その結果から今年度の出題テーマを想定します。想定問題も2問掲載していますので受験対策の参考にしてください。
問題文の構成は昨年までと変わらないはず
必須科目Ⅰの問題文は、過去6年のいずれも前文と(1)~(4)の4設問で構成されています。この問題文構成は、今年も変わらないはずです。
前文には、日本の社会情勢と社会ニーズが書かれており、前文の内容を踏まえて設問に解答することが求められます。
設問(1)には、課題抽出のテーマや解答条件が書かれています。解答条件としては、多面的な観点から3つ課題を抽出すること、観点を明記した上で課題の内容を示すことの2つが付くはずです。また、昨年度から課題抽出に当たっては、「投入できる人員や予算に限りがあることを前提に」という条件が付けられましたが、この条件は今年も付くと思います。
設問(2)では、抽出した3課題から最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題への複数の解決策を複数示すことが問われます。これまでは、解決策の提示数は指定されていませんが、3つの解決策を挙げるよう指定される可能性もあります。
設問(3)では、解決策を実行して新たに生じうるリスクとそれへの対策が問われます。以前は、解決策を実行して生じる波及効果と懸念事項への対応策を問うパターンもありましたが、今年は無いと思います。仮に後者のパターンで問われたとしても、リスクと懸念事項は同じことで、どちらも負の波及効果から派生することに変わりはありません。
設問(4)では、設問(1)~(3)を業務として遂行するに当たり、技術者としての倫理、社会の持続性の観点から必要となる要件・留意点が問われます。一昨年3月に技術者倫理要綱が改定されていますが、コンピテンシーは変わっていないので、これまでと同様に公衆の安全・健康・福利の優先、地球環境の保全・社会の持続性確保への認識を確認されると思います。
過去6年間の出題テーマを分析した結果
出題テーマとは、問題を解決して良い状況にする目標のことで、過去6年間の問題ではいずれも設問(1)の前半に書かれています。今年も例年通りだと思うので、設問(1)の前半に着目すれば、出題テーマは簡単に見つけられるはずです。
出題テーマは、課題を抽出するための目標ですから、前文の社会情勢や社会ニーズに深く関連してきます。過去6年間で出題された必須科目Ⅰの過去12問について、社会情勢、社会ニーズ、出題テーマを一覧表にすると次のようになります。
社会情勢としては、過去12問のうち人口減少が3回、自然災害が4回、老朽化2回、地球環境2回、デジタル対応1回が出題されています。社会情勢は、現代社会にとって不都合な状況が示されます。
社会ニーズとしては、各問題で言い回しは違いますが、いずれも持続可能な社会構築を挙げています。社会ニーズは、不都合な状況下にある日本の課題と捉えても良いでしょう。
出題テーマは、社会ニーズを達成するために、建設部門が実現すべき目標です。過去12問の出題テーマは、すべて違っています。社会情勢や社会ニーズが同じでも、出題テーマを毎回変えていることから、おそらく今年も過去問とは違う出題テーマになると想定されます。
不都合な社会情勢に関連する未出題テーマを想定
過去12問と同じテーマは出題されないとすると、今年の出題テーマは各社会情勢(人口減少・自然災害・老朽化・地球環境・デジタル対応)に関する未出題テーマになるはずです。社会情勢ごとに、ここ2,3年の社会問題を考えると、今年の出題テーマが次のように見えてきます。
人口減少では、生産性向上と担い手確保、連結型国土形成が出題済みなので、未出題の地方創成や生活サービスの確保などのテーマが想定されます。
自然災害では、安全安心の確保、風水害の防止削減、巨大地震への対応、復旧復興のDX活用が出題済みなので、未出題の複合災害対応や事前防災などのテーマが想定されます。
老朽化では、戦略メンテナンス、第2フェーズが出題済みなので、未出題の群マネ推進やインフラ再構築などのテーマが想定されます。
地球環境では、循環型社会とCO2削減吸収が出題済みなので、未出題のグリーンインフラ推進やサーキュラーエコノミーの推進などのテーマが想定されます。
デジタル対応では、インフラDX推進が出題済みなので、未出題のスマートインフラ構築やインフラデータの利活用などのテーマが想定されます。
複合災害への対応をテーマとした想定問題
昨年、能登半島での地震後の豪雨による被害拡大が社会問題として話題となりました。今年、相次いで公表された能登半島地震後の豪雨災害、首都圏における広域降灰対策、南海トラフ巨大地震対策に関する提言・報告では、いずれも異なる災害が同時または連続して発生する「複合災害」を想定した対策に言及しています。
複合災害は、過去にも多くの実例があり、今後も繰り返し直面する可能性が高い問題です。南海トラフ巨大地震の発生確率は、今後30年以内に70%~80%とされていますが、豪雨災害は毎年どこかで必ず発生しているので、地震と豪雨の複合災害は相当高い確率で起こり得ます。
災害が同時または連続して発生すると、被害が拡大し対応も複雑化するため、従来の単独災害対策では十分に対応できません。そのため、複合災害への備えは国民の生命・財産を守る上で重要なテーマなので、今年出題される可能性があると思われます。
我が国は,地震,噴火,台風,豪雨,豪雪など, 様々な自然災害が発生する地形・気象特性を有している。そのため、異なる自然災害が時間差をおいて連続発生する複合災害が,全国各地で発生する可能性がある。複合災害では,先発の自然災害の影響が残っている状態で,後発の自然災害が発生することにより,単発の災害に比べて被害が拡大し復旧対応も困難となる。
石川県輪島市では,令和6年1月の大規模地震で上流渓床部に堆積していた土砂が、同年9月に記録的豪雨により中小河川の下流まで流下し,避難の遅れによる人的被害が発生している。
今後発生しうる複合災害に対し,事前の防災・減災対策を効率的かつ効果的に進めていく必要があることを踏まえ,以下の問いに答えよ。
(1)今後発生しうる複合災害に対し,被害の防止・軽減に向けた対策を進めていくに当たり,投入できる人員や予算に限りがあることを前提に,技術者としての立場で多面的な観点から3つの課題を抽出し,それぞれの観点を明記したうえで,課題の内容を示せ。(※)
(※)解答の際には必ず観点を述べてから課題を示せ。
(2)前問(1)で抽出した課題のうち,最も重要と考える課題を1つ挙げ,その課題に対する複数の解決策を示せ。
(3)前問(2)で示したすべての解決策を実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について,専門技術を踏まえた考えを示せ。
(4)前問(1)~(3)を業務として遂行するに当たり,技術者としての倫理,社会の持続性の観点から必要となる要件・留意点を述べよ。
インフラ再構築をテーマとした想定問題
インフラ老朽化は大きな社会問題になっています。15年後の2040年には、道路橋の約75%、トンネルの52%、河川管理施設の約65%が、一般的な耐用年数の50年を超えると予想されています。重要インフラの1/2~3/4が、一気に機能低下するという極めて深刻な事態です。
H24の笹子トンネル崩落事故以降、各分野では法制度を改正して老朽化対策に取組んできました。しかし、今年1月発生した埼玉県八潮市の道路陥没事故は、これまでの老朽化対策では、国民の安全を守れないことを浮き彫りにしました。
来年度予算に向けての骨太方針では、人口減少が進む中でのインフラ老朽化対策の在り方がインフラ整備の主テーマになる模様です。今後は、将来の人口減少を見据えてコンパクトなまちづくりやインフラのダウンサイジングへの要求が強まると思います。
さらに、現在審議中の次期社会資本整備重点計画の素案では、人口減少社会への対応として、地域経済の核となる集積づくりと広域連携、地域の将来像を踏まえたインフラの再構築が示されています。
このように、インフラの老朽化と人口減少を背景に議論が進んでいる状況から、インフラ再構築が、今年の出題テーマになり得ると思います。
我が国のインフラは,今後,建設から50年以上経過する施設の割合は加速度的に増加する。インフラの多くを管理している市区町村では,財源不足に加え,土木系を含む技術系職員数が減少し,全国の4分の1の市区町村で技術系職員が配置されていないなど,メンテナンスに携わる担い手の不足も深刻な状況となっている。
一方,人口減少が急激に進んでいる市区町村では,買物弱者の増加,救急医療や出産,子育て,福祉・介護等へのアクセス困難など,真に必要な日常的な生活サービスに対する生活者の暮らしの安全・安心を失いかねない深刻な状況となっている。
今後は,人口減少時代に対応した,まちづくり・地域づくりと一体となったインフラストックのマネジメント体系に移行することが求められることを踏まえ,以下の問いに答えよ。
(1)地域の将来像に即したインフラの再構築を進めるに当たり,投入できる人員や予算に限りがあることを前提に,技術者としての立場で多面的な観点から3つの課題を抽出し,それぞれの観点を明記したうえで,課題の内容を示せ。(※)
(※)解答の際には必ず観点を述べてから課題を示せ。
(2)前問(1)で抽出した課題のうち,最も重要と考える課題を1つ挙げ,その課題に対する複数の解決策を示せ。
(3)前問(2)で示したすべての解決策を実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について,専門技術を踏まえた考えを示せ。
(4)前問(1)~(3)を業務として遂行するに当たり,技術者としての倫理,社会の持続性の観点から必要となる要件・留意点を述べよ。
下記の電子書籍では、この記事に掲載している2つの想定問題を使って、解答骨子の作成プロセスを解説しています。